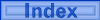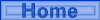わんだふる☆わーるど
「おおっ、聡じゃないか。よう来たのう」 あれ、なんでじいさんがあんなとこに立ってるんだ? 「ほれほれ、そんなとこに突っ立っとらんでこっちへ来んか」 じいさん、まさかおれを向こうの世界に連れてく気か? 「しかし、今日はお客さんが多いのう」 ?何言ってるんだ? 「お〜い、嬢ちゃん。そんな所に隠れとらんで出てきたらどうかのう」 じいさん、誰かを呼んで……る……… 「う………ん?」 夢……だったんだろうか? それにしては妙にリアルだったな。 朝の光を顔に浮けたおれは、その光でどうやら覚醒したらしい。 ん?光? 確かカーテンは締めたはずなんだが…… そう思い、おれはゆっくりと瞳を開ける。 「あ、お目覚めになりました?」 「?!!!!」 数秒の間、おれの心臓は止まっていたかもしれない。 な、なんでこんな至近距離にエル、いや今日からは絵里か、の顔があるんだ? 「……?どうかしましたか?」 至近距離でおれの瞳を見つめ、絵里が尋ねてくる。 この体勢、他人がみたら絶対あらぬ誤解を受けるぞ。 まあ、ここはおれの部屋で、他人が見てるなんてことはないだろうが、どこかから殺意のこもった視線を感じるのは気のせい だろうか? 「……あのさ」 やっとのことでおれは絵里に言葉をかけた。 「はい、なんでしょう?」 「ちょっと、どいてほしいんですけど……」 「あ、そうですね。これは気がつきませんでした」 そう言って絵里はひょいっとベッドの上から跳びのいた。 「ところで、今何時?」 「ええっとですね……7時33分ですね」 「え?!」 マジですか? おれは7時にタイマーをセットしてたはずなんだけどな………… 「なあ、7時ごろその時計鳴らなかったか?」 そう、この時計のアラームはやたらとでかい。 姉貴の部屋まで響くらしく、結構姉貴が愚痴ってたっけ。 「ええ、確かに鳴ってましたけど、私が止めちゃいました。もしかして、駄目でしたか?」 うう、そんな哀しげな目をしないでくれ。 「いや、駄目ってわけじゃ……ところで、絵里はいつ頃おれの部屋に来たんだ?」 「はい、昨日の夜ですけど」 「夜〜〜〜〜?!!」 おいおい、本当によく見るとおれのベッドの隣に布団がひいてあるよ。 おれは一度熟睡すると火事になっても起きないんじゃないかって言われてるからな〜。 全く気がつかなかった。 う〜ん、惜しいことを……って、おいおい、違うだろ。 しっかし、大丈夫なのか、この娘は? 「あの、一人だとなかなか寝付けなかったもので……」 ううっ、やめてくれ。その目でおれを見ないでくれ〜。 「わかったよ。今日から一緒に寝てやるよ」 「はい!」 おれは、得体のしれない敵意の視線を感じながらも、絵里の要求を飲むしかなかった。 7/18 第31話 「Morning Call」
・・・・・ さて、それじゃあおれも本格的に起きるかな。 と、その前に…… 「絵里」 「何でしょう?」 「その、着替えたいんだけど」 「はい、制服でしたらここに用意してありますけど」 絵里の見つめる先にはいつの間にか用意されていたアイロン台で綺麗にしわをのばされたおれの制服が確かに用意されていた。 「うむ、ご苦労………って、そうじゃなくてさ。ちょっとこの部屋から出ててくれないか?」 「どうしてですか?」 ま、またその瞳でおれを見ますか?! 「……わかった、じゃあ出ていかなくていいからちょっと後ろを向いててくれ」 おれは精一杯の妥協案を絵里に提案した。 「は〜い」 絵里は今度は素直にくるっと後ろを向いた。 よし、今だ! おれは松坂の速球さえも越える速さで着替えを済ませた。 「よし、いいよ」 「わ〜、聡さんが変身してます」 ……この娘、絶対なにかがズレてるよ。 向こうの世界でもこんな感じだったのかな。 ケイも基本的な性格は変わってないっていってたし。 ……うう、なんだかケイの苦労を垣間見たような気がしたぞ。 そしておれたちはいつの間にか朝食をとっていた。 「!聡さん、このお水、黒いですよ?」 「ああ、それはコーヒーといって苦いけど眠気覚ましにはぴったりの飲物なんだ」 うちの朝食は決まってパンとコーヒーだ。 理由は簡単。 うちは両親ともに味噌と納豆が駄目なのだ。 おれは別になんともないんだが。 まあ、毎日の習慣なので朝起きたらコーヒーを作ることにしている。 で、おれが作ったそのコーヒーを絵里が珍しそうに見てるってわけだ。 「飲めるんですか?!」 「当たり前だろ。ほい」 そういっておれは絵里に角砂糖の入ったびんを渡す。 ちなみにおれはブラック派だ。 「これは……お砂糖ですか?」 「そうだよ。苦かったらそれをコーヒーの中に入れるのさ」 「はぁ……」 おれは焼きあがったトーストにいちごジャムを塗りながら絵里に答えた。 それでも絵里はコーヒーを凝視したままだ。 しっかし、コーヒーは知らないのに砂糖は知ってるのか。 一体、絵里のいた世界ってどんなとこだったんだ? まったくもって謎だ。 7/24 第32話 「Breakfast」
・・・・・ 「ごちそうさん」 「ごちそうさまでした」 朝食をすませたおれと絵里は、食後の挨拶をかわした。 結局、絵里はコーヒーを飲まなかった。 まあ、人の好みはそれぞれだから構わないけど、食わず嫌いはだめだろ。 あ、この場合飲まず嫌いか。 別に強要するつもりもないけどさ。 「さて、そろそろ行きますか」 「?どこか出かけるんですか?」 「だぁっ!学校だよ学校!」 「ああ、そうでしたね」 ……もしかして、わざとか? 深く考えると恐いものがあるから考えないでおこう。 しっかし、一緒に学校行くとなるとなんかこっ恥ずかしいな。 女の子と一緒に登校するのなんて小学校以来か? 知り合いに見つかったら厄介なことになりそうだけど、見つからないのは不可能に近いからな。 なんとか絵里と別々に学校に行けないものか…… 「なあ、絵里」 「はい」 「学校の場所ってわかるか?」 「いいえ」 ……やっぱり一緒に行くしかなさそうだ。 おれは観念して、絵里を伴い玄関へと向かった。 「ふぅ……」 おれの口から自然とため息がもれる。 何事も起こらなければいいが…… そう思いながらおれは扉を開けて、通い慣れた通学路へと歩きだそうとしたその時、目の前に人の気配を感じてそちらの方 を見た。 「ん?」 「あ……」 そこに立っていたのは、小中高で全て一緒のクラスという偉業を成し遂げたハイパー腐れ縁、柳瀬梓だった。 「ああ、なんだ梓か。どうしたんだ?そんなとこに突っ立って」 しかし梓は、おれの問いかけには答えずに猛ダッシュで駆け去っていった。 さすが陸上部のホープ。青いハリネズミ君もますます真っ青のスピードだ。 しかし、どうしたんだ?あいつ。 「どうしたんでしょうね、あの人」 いつの間にか隣に来ていた絵里がおれに聞いてきた。 「さあ………あ!絵里、いつからそこに居た?」 「えと、聡さんが外に出たすぐ後からですけど」 ということは………見られた?! やばい、やばすぎる。ものすごい誤解を梓に与えたかもしれないぞ。 うう〜、絶対学校で何か言われる〜。 もしかしたら口だけじゃすまないかもしれない…… 覚悟しとこ。 「どうしたんですか?」 「いや、なんでもない」 少々ブルーになりながらも、おれたちはやっとのことで学校に向かうのであった。 7/28 第33話 「Go To School」
・・・・・ 学校へ向かう道すがら、おれは妙に視線を感じていた。 まあ、多分絵里を見てるんだろうけど…… 「なあ」 「はい?」 「ちょっと、離れて歩かないか?」 そう、腕こそ組んでいないが、絵里は文字どおりおれにぴったりとくっついて歩いていたのだ。 まるで恋人同士のように。 「なんでですか?」 そういっておれの顔を覗きこむ絵里を見ると、おれは強いことは言えなくなる。 っていうか、なんか卑怯だ。 結局、学校に着くまで、絵里はおれの隣に寄り添って歩いていた。 不思議なことに、知った顔には出会わなかった。 まあ、それが救いといえば救いか。 学校に着いたおれは、教室にも寄らずに真っ直ぐ職員室にむかった。 「失礼しま〜す」 扉を軽くノックして扉を開ける。 まだ朝早いからか、職員室にも人影はまばらだ。 「桐生先生!」 おれはおれのクラスの担任、桐生晴彦の姿を見つけるとすぐさまそこに駆け寄った。 「おはようございます」 「ああ、おはよう。しかし、氷上。今日はえらく早いな。なにかあったのか?」 「はい、実は……」 そう言っておれは絵里を紹介した。 「ほう、このお嬢ちゃんが例の転校生か。お前の家に居候してるんだってな」 「まあ、平たく言えばそうなりますけど……」 「なんだ?違うのか?」 「違いませんよ」 絵里が微笑みながらフォローを入れてくれた。 「ふ〜ん、まあいいや。ところで、え〜と……」 「絵里です。早瀬絵里」 「ああ、そうそう、早瀬さん。ちゃんと校長には挨拶してきたかい?」 「いいえ」 「じゃあ、早いとこ行ってきな。氷上、案内は任せたぞ。俺はちょっと朝の内に片付けときたいことがあるからな」 「はい、わかりました」 そういっておれたちは職員室を後にした。 7/30 第34話 「staff room」
・・・・・ そんなこんなで、おれたちは校長室にたどりついた。 「んじゃ、絵里。校長に挨拶してこいよ」 「はい」 「そんじゃな」 「え?一緒に入るんじゃないんですか?」 不安げな瞳でおれを見つめる絵里。 「う〜ん、そうしたいのはやまやまなんだけどさ。もうすぐホームルームも始まっちまうし」 「……そうですか。それなら仕方ありませんね」 寂しそうに呟く絵里。 「じゃ、また後でな」 「はい」 おれは、絵里が校長室の扉をノックする音を背にして、その場を後にした。 おれは教室の扉を開いた瞬間、殺意の波動を感じた。 それは教室中が感じたようで、さっきまでの騒然とした雰囲気が一瞬で静寂に変わる。 ある程度予想はしていたが、まさかこれほどとは…… 今回は本気でヤバイかもしれない。 おれは意を決して、その殺意を周囲にまき散らす張本人に朝の挨拶をかわした。 「……おはよう」 緊張のあまり、少し声が裏返ってしまった。 しかし、今この教室で殺意を放ち続けているその人物、柳瀬梓は何の反応も示さない。 ……マジだな、こいつ。 困ったことに、おれと梓の席は隣同士だった。 こりゃ、今日は授業どころじゃないな…… おれは、梓が放つ殺意を全身で受け止めながら自分の席についた。 ………………………だ、だめだ〜〜〜!! 気がつくと、おれは男子トイレの個室に入っていた。 「あれ、おれはなんでこんなとこにいるんだ?」 ちらっと腕時計に目をやる。 まだHRは始まっていないようだ。 とりあえず、おれは地獄と化した教室に戻ることにした。 「ふ〜〜っ」 個室の扉をあけると、いきなりこっちが脱力するような気の抜けた声が聞こえてきた。 少しコケそうになりながら、その声の主を見ると同じクラスの神田道夫だった。 「おいっす、道夫」 「おお、聡。なんだ、腹の具合でも悪いのか?顔色が悪いぞ」 「いや、そういうわけじゃねーんだけどさ」 「そうか。ああ、そういやなんか教室が殺伐とした雰囲気だったんだけど、お前なんか知んねーか?」 「お前にまでわかっちまうのか……」 道夫は非常にマイペースなやつで、余り回りのそういう雰囲気とか匂いとかには鈍いやつなんだが…… そんな道夫にまでそれとわかるとは、梓の怒りはおれの想像をはるかに越えていたらしい。 「ん?どうしたんだ?ますます顔が青くなったぞ」 「あ、いや、なんでもないんだ」 「?おかしなやつだな。まあいいや。さっさと教室に帰んべ」 「……ああ、そうだな」 おれは重い足取りで、道夫と共に教室に戻ることにした。 8/1 第35話 「killing wave」
・・・・・ おれは意を決して教室の扉を開けようとした。 が、本能がおれの身体を押しとどめる。 「何やってんだ?おめえ」 道夫が不思議そうな顔でおれに尋ねてくる。 「あ、ああ。道夫、悪いけど先に教室入ってくんねえか?」 「まあ、いいけどよ」 元来、細かいことは気にしない道夫は、おれのとても普通とは思えない硬直ぶりを気にする風もなく、ささっと教室に入っ ていった。 (………あれ?) 道夫が扉を開けた瞬間、殺意の嵐がおれを襲ってくると思っていたが、いつまでたってもそれらしい波動を感じることはな かった。 ちょっと拍子抜けだ。 そして、道夫から遅れること約2分、おれは再び教室に足を踏み入れた。 教室は、いつも通り雑然としていた。 さっき、おれが入ってきた時の静寂が嘘のようだ。 その理由は単純だった。 今は梓が席を外しているのだ。 これで、おれはしばしの休息を得ることが出来ると思ったのだが、世の中そんなに甘くなかった。 「ねえ、聡くん」 席につくなりおれは梓の親友で、おれにとっても中学からの女友達である的場由美が声をかけてきた。 ちなみに、女子でおれのことを名前で呼ぶのは梓と由美くらいだ。 あ、そういや絵里もそうだっけ。 「なんだ、由美」 「なんだじゃないでしょ。いったい梓ちゃんに何したの?」 ………やはりそうきましたか。 「別に。何もしてね〜よ」 そう、別にやましいことなど何もしてないのだ。 ただちょっと、記憶をなくした別の世界からやってきた女の子と朝一緒に家から出てくるとこを見られただけで……… しかし、梓は変なとこで真面目だから何いっても聞いてくんないだろ〜な。 「嘘。何もしないで梓ちゃんがあんなに怒るはずないわ。ねえ、本当のことを教えてちょうだい」 う〜ん、どうしたもんか。 ここで由美に本当のことを喋っちまえば、梓をなんとか説得してもらえるかもしれないが……… 「すまん。事情は後で話すよ。それと、梓にもおれからきちんと話しとくよ」 「そう。それならいいんだけど」 そう言って由美は自分の席へと戻っていった。 そうだよな。 これはおれと梓の(あと絵里もか?)問題だ。他人を巻き込んじゃいけないだろう。 それにしても、梓、なんであんなに怒ってたんだろう。 よくよく考えてみると不思議だ。 おれがあいつの弁当盗んで早弁した時も、授業中居眠りしてる時にノートに落書きした時も、借りてたCD割っちまった時も、 あんな怒りかたはしなかったよな。 やっぱり、話してみるしかないか。 8/3 第36話 「Friends」
・・・・・ おれがそんなことを考えていると、教室に突然緊張が走る。 そう、梓が戻ってきたのだ。 ただ、幾分落ち着いたのか、さっきのような触れるだけで意識が遠のいていくような殺気は薄れていた。 といっても、まだ完全に怒りがおさまったわけではなさそうだけど…… そして、おれが玉砕覚悟で梓に話しかけようとした時、意外なことに梓のほうから声をかけてきた。 「サトシ、ちょっといい?」 梓はおれのことを社会現象にまでなった某大ヒットアニメのキャラクターのようにカタカナで呼ぶ。 実はあれはおれが小学校の頃の活躍をモデルに……してるわけもない。 第一、黄色い電気ネズミなんて飼ってた覚えもないしな。 「ああ……」 拒否権などとっくの昔に剥奪されているおれは、梓の言葉にうなずくことしか許されなかった。 そしておれと梓は、HRが始まる直前の教室を後にした。 「あの娘、誰?」 教室を出るなり、いきなり梓が聞いてきた。 相変わらずストレートなやつだ。 教室から声は聞こえない。 たぶん、いや、絶対にみなさん聞き耳をたてているはずだ。 そんなことしなくても、梓の声は良くとおるので、嫌でも聞こえると思うんだが…… 「あれは、親戚の娘だ」 答えないわけにもいかないので、おれは当たり障りのないことを答えることにした。 いきなり、「あの娘は異世界からきて、しかも記憶をなくしてる」とか本当のことを言って反応を楽しんでもよかったが、 今そんなことやったらおれがこの世から消えそうな気がしたからやめておいた。 「親戚?」 「そうだ」 「あんたの家って外人に親戚がいるの?」 「あの娘はクウォーターなんだ」 「ふ〜ん。まあ、それはいいわ。なんで今日の朝、あの娘はあんたと一緒にあんたの家から出てきたの?」 教室内が少しざわつく。 「うちで預かってるんだよ。なんか手違いで入居日が一週間延びたみたいなんだ。だからうちで泊めてあげることにしたの」 「じゃあ、一週間、あんたはあの娘と二人っきりで暮らすのね」 「そうだよ……って、え?!」 教室内がさらにざわつく。擦りガラスごしにいくつもの人影がみえる。 「な、なんで梓がそんなこと知ってるんだよ」 「ふん。うちの親父はあれでも商工会議所の会長をやってるのよ。商店街の福引だって親父の企画なんだ。だから、サトシん ちの両親が昨日から温泉旅行に行ってるってことはちゃんとわかってるんだから」 そういやそうだ。 おれは親しいから全然そんな風には感じないけど梓ん家の父親は商店街のお偉いさんだったんだ。 「……しょうがねーじゃねえか。重なっちまったんだから」 「サトシ。あんたあの娘に手出してないでしょうね?」 「ば、馬鹿!するか、んなこと」 そんなことしたら、梓だけではなくケイにまで殺されてしまう。 「ま、サトシにそんな甲斐性なんてないとは思ってたけどね」 そう言って梓は悪戯な笑みを浮かべる。 そう思ってんなら、あんな殺気放つなって〜の。 ん?そういや、もう梓からあの異様な気配は感じない。 どうやら普段の梓に戻ったらしい。 「そういえば、あの娘ここの制服来てたみたいだけど……」 「ああ、今日この学校に転入するんだ」 「クラスとか、わかる?」 「いや」 「そう……ま、いいわ。許したげる」 いったい何をどう許されたのかわからないが、これにて一件落着といったところだろうか。 「じゃ、教室に戻りましょっか」 「おう」 8/5 第37話 「interrogation」
・・・・・ おれと梓が教室に戻ると、はかったようにHR開始のチャイムが鳴った。 そのおかげでおれは友人たちの好奇心旺盛な視線を受けることを免れた。 なぜなら、 「よ〜しみんな席に着け〜」 うちの担任の桐生先生はいつもチャイムと同時に教室に入ってくるからだ。 ま、その分HRが終わるのも早いけどさ。 どっちにしろ、今は嵐の前の静けさというかインターバルというか、とにかくそんな感じで、もうすぐ色々な質問攻めにあう、 はずだった。 「いきなりだが、みんなに紹介したい人がいる」 と、桐生先生がなんだかいつもとは違う口調で喋っている。 ちゅうか、なんか結婚相手を披露するみたいな物言いだった。 クラスの大半もそんなことを感じたのか、回りを見回すとほとんどが「キョトン」という目をしていた。 多分、おれもあんな目をしてただろう。 「おい、入ってこい」 そう桐生先生に呼ばれて教室にてくてくと入って来たのは…… 絵里だった。 「先生!」 いきなりそう叫んで立ち上がったのは、学級委員長の相田美智子だった。 しかし、彼女を名前で呼ぶのはごく一部の人間だけで、クラスの大部分から「委員長」と呼ばれている。 もちろんおれもそのうちの一人だ。 これは委員長の宿命だろう。多分。 「どうした、相田」 彼女を名前で呼ぶ数少ない人間の中の一人、桐生先生が委員長に問い返す。 すると委員長は、 「式はいつ挙げるんですか?」 などと、とんでもないことを言い出した。 桐生先生も最初なにを聞かれたか理解出来なかったらしく、10秒ほど黙ったままだったが、 「おいおい、何の冗談だ。おれが誰と結婚するって?」 と軽く受け流すことに決めたようだ。 しかし委員長は意外としつこく、 「そこにいる彼女とです」 と、もはや決定事項かのように自信たっぷりに言い切る。 あの根拠のない自信はどこからくるのかねえ。 「そんなわけあるかよ。彼女は今日この学校に転校してきた転入生だぞ。それに、もし俺が結婚するとしてもだ、なんでいち いちお前たちにその相手を紹介しなきゃいけないんだ?」 確かに、もっともな意見だ。 「それに、彼女は氷上と一緒に住んでるんだ。俺もそんなに野暮じゃない。な?」 と言ってこちらに微笑んできた先生の顔が、一瞬、悪魔に見えた。 んとに、あの先生はいつも一言余計なんだよな。 これでまた頭痛の種が一つ増えたような気がする。 「もう、質問はないな。よし、じゃあ早速自己紹介してくれ」 「はい」 そういって絵里はおずおずと黒板に自分の名前を書き始めた。 ………緑色のチョークで。 「早瀬絵里といいます。よろしくお願いします」 8/9 第38話 「selfintroduction」
・・・・・ 深々と頭を下げた絵里が頭をあげると、教室中から拍手がわきおこった。 何故? 「はい、静かに。それじゃ、早瀬の席は……おっ、ちょうど氷上の隣が空いてるじゃないか」 「へ?」 確かにおれの右隣の席に人は座ってない。 が、しかし、 「先生、そこは波多野君の席ですけど?」 そう、そこは波多野繁の席なのだ。 「ああ、波多野は今日風邪で休むそうだ。他に空いてる席もないみたいだから少しの間そこに座っててもらうだけだ。 ということで氷上、1時間目が終わったら新しい机と椅子を持ってきてやってくれ」 「……わかりました」 別に今から取りに行ってもいいんじゃないかと思いつつも、おれは先生の言葉に従うことにした。 「よろしくお願いします」 「ぬおっ?!」 何時の間にか隣の席に移動していた絵里が丁寧に挨拶してきた。 「あの、どうかしましたか?」 「いや、なんでもない」 「おい、そこのお二人さん。そろそろホームルームを始めたいんだが、いいのかな?」 うっ、先生がなんだか「青春って素晴らしい」ってな顔をしてこっちをみてるぞ。 「え、ええ。お構いなく……」 こうして、いつも通りではない始まりだったホームルームは、いつも通りの終わりを迎えた。 「へ〜、ほんとに聡君と一緒に住んでるんだ」 「はい」 ホームルームが終わった後、やはりというかなんというか、絵里は取り囲まれた。 そのあおりをくらって、おれはエスケープに失敗してしまったのだが…… 「ちっくしょう、聡!こんな可愛い子どこで拾ってきたんだ?」 「こらこら、そんなこといったら絵里ちゃんに失礼でしょ」 いや、どっちかっていうと拾ってきたのに近いんですけど。 などとはとても口に出せやしない。 絵里は絵里で次々と繰り出される質問に必死に答えようとしている。 「好きな食べ物は?」 「カレーです」 「趣味は?」 「お昼寝です」 「スリーサイズは?」 「謎です」 「将来の夢は?」 「お嫁さんです」 「好みのタイプは?」 「聡さんです」 「おお〜〜〜〜!!」 野次馬の視線が一斉にこっちに向けられる。 ……そういや昨日、冗談で好みのタイプって聞かれたらおれって答えとけって言ったんだった。 「これは」 「もしかして」 「相思相愛ってやつですか?!」 ちょっと待て! おれの意思を無視するんじゃね〜!! 10/6 第39話 「question」
・・・・・ 「お〜い、お前ら。とっくにチャイムは鳴ってるぞ?」 「桐生先生!いつからそこに?!」 驚いた由美が声をあげる。 由美の視線の先をたどると、確かにそこには何時の間にか野次馬の群れに紛れ込んだ先生の姿があった。 ……全く気付かないおれたちもおれたちだが、気付かれない先生も先生だ。 「さ、みんな早いとこ席に着こうな」 「は〜い」 桐生先生の登場により、やっとおれの周りの喧騒はおさまった。 ったく、もうちょっと早く止めてくれりゃあいいのに。 ……いや、あの先生のことだ、きっと面白がってたに違いない。 「よかったな、氷上。これでお前と早瀬は公認カップルってわけだ」 やっぱり。 桐生先生の担当は現代国語。 というわけで、今日の1時間目は現国なのだ。 ちなみに、やはりというかなんというか、おれと絵里は机をくっつけて授業を受けていた。 まあ、絵里は教科書も何も持たないのだからそれは仕方がない。 が、しかし。 何故、おれをジッと見つめる? 授業中なんだから黒板見ようぜ、黒板を。 「ん〜と、じゃあ次を……高橋、読んでくれ」 「はい」 あ、今とばされたぞ。 さっきはおれの前の江藤が当てられたから、絶対次はおれだと思ったんだけどな。 ほっとした半面、ちょっと寂しくもある。 複雑な心境だ。 あ!そういえば。 「絵里、お前確か字読めなかったんだよな?」 おれは小声で絵里に話しかけた。 そういやすっかり忘れてた。 授業以前の問題じゃねーか。 「いえ、読むことはできます。昨日覚えましたから」 絵里も小声でおれに話してくる。 「覚えた?どうやって?」 「さあ?」 …………… あやうくおれは吉本新喜劇にひけをとらないコケを披露するところだった。 やはりこの娘について深く考えてはいけないようだ。 そして、1時間目の授業は滞りなく終了した。 10/12 第40話 「First Lesson」
第41話 「School Days I」へ