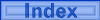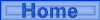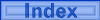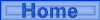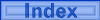AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
ハッピータウン!!
第十一話 「時、解けゆく心」
「ねえ、ちょっと気になったんだけど」
『HONEY BEE』を後にしてすぐ、秋次が椎奈に問い掛けてきた。
「ん、どうした?」
「さっき、リアンさんがスフィーのこと『姉さん』って呼んでたけど……」
「ああ、よく間違えられてるけど、確かにスフィーの方が姉さんなんだぜ」
「ええ?!!!」
秋次の顔は、自分で見れないのがもったいないくらい、間の抜けた顔になっていた。
それもそのはず、スフィーの外見はどう見ても美悠よりも年下としか思えないからだ。
「おいおい、そりゃ驚きすぎだろ。まあ、無理ないかもしんねーけどさ」
「ちなみに、いくつなの?」
「ん〜と、リアンちゃんが19で、スフィーちゃんが21だったと思う」
美悠にかかれば、年上でもちゃんづけらしい。
呼び捨ての椎奈も椎奈ではあるが。
「にじゅういち……」
驚きのあまり、秋次の声はひらがなになってしまっていた。
「まあ、細かいことは気にすんな」
「そうだよ」
「……そういう問題なの?」
かなり納得のいかない秋次ではあったが、二人にそう言われるとなんとなくどうでもいいことのような気がしてくるので
不思議だ。
「さて、これからどうするか」
椎奈は、どうやらこれから先の予定を考えていなかったようだ。
「秋次、どっか行きたいとことかねーか?」
「いや、突然そんなこと言われても……第一、この町のことよく知らないし」
「そういやそうだったな。町の案内してやってもいいけど、普通に案内するのはつまんねーしな」
普通でいいのに、と心の奥で思う秋次であったが、あえて突っ込まないことにした。
普通じゃない町案内というのもちょっといいかな、などと思う心のほうが強い秋次なのであった。
「う〜ん」
「う〜ん」
「う〜ん」
道の片隅で三人が腕組みして悩む姿は傍から見て異様だ。
実際、道行く通行人は彼らを無視するか、遠巻きに冷たい目で見ているが、秋次たちは全く気づいていない。
「よし!」
突然、椎奈が声をあげた。
「何か名案が浮かんだ?」
「いんや」
勢い良くコケる秋次&美悠。
「お姉ちゃん!」
「まぎらわしいことはやめてくれないかな……身体がもたないよ」
「ああ、悪かったよ。とりあえず、ここで悩むのもなんだし、一回家に戻らないかって言いたかったんだ」
少々バツが悪そうに、頬をかきながら椎奈が言う。
「お姉ちゃん」
「それ」
「ナイスアイディア!」
秋次と美悠の声が、見事にシンクロする。
「おめーら、いつのまにそんなコンビネーションを覚えたんだ?」
「へへ」
秋次と美悠は顔を見合わせて笑うだけで、椎奈の問いに答えようとしない。
(美悠のやつ、大分“地”が出るようになったじゃねーか)
そんな美悠の様子を、椎奈は姉の目で見つめていた。
(これなら、もう安心だな)
「おい、ちょっと待てよ」
椎名は、前を行く二人に追いつき、三人で家路を歩いた。
「ただいま〜」
勢い良く扉を開け、椎奈が大きな声で帰宅を告げる。
「あら、椎奈。早かったわね」
ちょうど玄関付近にいた永佳が、椎奈たちの方に顔を向けた。
「姉貴こそ。入学式はもう終わったのか?」
「え、あと、それがね」
「ん?どうしたんだよ、姉貴」
「入学式は明日だよ」
突然、永佳の背後からした声に、全員の視線がそこに向かう。
「和樹さん!」
慌てたように、永佳が叫ぶ。
「なんだ和樹。来てたのか」
「よ、椎奈。美悠ちゃんもこんにちわ。それと……秋次君、だね」
「あ、はい」
「俺は千堂和樹、たまにここでアシスタントをさせてもらってるんだ」
「アシスタント?」
「ちょっと待て和樹、明日ってどういうことなんだ?」
「椎奈、そのことはもういいでしょ?」
永佳は、必死でその話題を避けようとしているようだ。
「まあ、いいじゃないか。それはそうと、君たち早く家に上がりなよ」
「そうだな。じゃあ、話しはリビングでゆっくり聞かせてもらうぜ、姉貴」
「うぐぅ」
何故か、似てないあゆの物真似をしている永佳であった。
・・・・・
第十二話 「画、表現すべき場」
「で、今日が入学式じゃなかったのか?」
リビングに着くなり、椎奈が永佳にたずねた。
「ま、そういうことになるわね」
すでに諦めたのか、永佳が投げやりに答える。
「ったく、姉貴はやっぱりどっか抜けてんだよ。だって今日は日曜だぜ、日曜!つまりお休み。そんな日に入学式なんて
おかしいって思わなかったのかよ?」
「う……そりゃ私だって少しは思ったわよ。大学に行く道もやたらと人が少なかったりしたし……」
「気づけよ!」
「でもでも、もしかしたら私が遅れてるだけで、式はとっくに始まってるのかもって思っちゃたら不安で……」
「だったら何で腕時計つけないんだよ?」
「だって、時間に縛られてるみたいで嫌じゃない?」
「そんなんだから姉貴は時間にルーズすぎるんだよ!」
「まあまあ二人とも落ち着いて」
かなり横のほうにそれかけた話題を、和樹が元に戻そうとする。
「大体、姉貴は変なとこばっかり頑固なんだよ。和樹からも言ってやってくれよ」
が、会話の主導権はどうやら完全に椎奈と永佳に握られてしまっているようだ。
「え、まあ少しは時間を気にしたほうがいいとは思うけど。でも、まあ時計を持つかどうかは個人の自由だからね」
「そうですよね、和樹さん」
「甘い、甘いぞ和樹!姉貴には絶対に時計を持たせるべきだ!そうしないと、例え世界中の時が止まっていても姉貴だけは
気づかずに動いてるに違いない!!」
「それはなんだか楽しそうね♪」
「あの、お取り込みのとこ申し訳ないんですが……」
今まで全く蚊帳の外であった秋次が、右手を控え目に挙げて発言の許可を求めた。
「ん、どうした?」
「出来れば、そちらの方を紹介してくれると嬉しいんですけど……」
そう言って秋次は和樹の方に視線を向けた。
「ああ、そう言えば秋次さんは和樹さんとは初対面なんでしたっけ」
「悪ぃ悪ぃ、んじゃ和樹、ちゃっちゃと済ませちゃってくれ」
「わかったよ。俺の名前は千堂和樹、って名前はもう言ったか。で、なんでこの家にいるかっていうと……」
「お〜い、和樹く〜ん」
と、和樹の言葉を遮るように、上のほうから声が聞こえてきた。
「あ、やべ。先生にコーヒー頼まれてたんだった。は〜い、すぐ戻りま〜す!」
そう言って和樹はトタトタと台所に向かっていってしまった。
「先生?今の声って、稔叔父さんの声だよね?」
「うん」
今まで秋次の隣で事の成り行きを見守っていた美悠がすぐに返事をする。
「なんで先生なの?」
「あれ、秋次さん、父さんの仕事って知りませんでしたっけ?」
「うん。先生ってことは……お医者さん?」
「うーん、惜しい。今はもう医者じゃないんだ」
「パパね、漫画家さんなの」
「漫画家?!」
「知ってますか?『夏樹隆也』って名前」
「知ってるもなにも、週刊誌に2本、月刊誌に3本もの連載を抱える売れっ子の漫画家じゃ……って、え?」
「そう、その『夏樹隆也』が遠藤稔、つまりあたいらの親父ってことさ」
「そうだったんだ……じゃあ、和樹さんは叔父さんの手伝いに?」
「うん。なんでも『春コミ』で知り合ったんだって。それからたまに手伝ってもらってるみたいなの」
「じゃあ、和樹さんももしかしてプロ、とか?」
「いいえ。和樹さんはまだプロではありませんけど、プロを目指して頑張ってるみたいです。ただ、和樹さんの周りの方
の噂によりますと、そっち方面ではもうかなり有名だそうです」
「そっち方面っていうのは……」
「同人誌即売会。まあ、いわゆる『こみっくパーティー』、通称『こみパ』ってやつだな」
「『こみパ』……」
さすがに漫画家の娘だけあって、3人ともかなりその分野については詳しいようだ。
多分、稔に連れられて実際に何度も足を運んでいるのだろう。
一方秋次のほうは、名前くらい聞いたことはあっても、実際にそれを体験したことはない。
「ん、何だ?行ったことないのか?」
「うん」
「なら、今度連れてってやるよ。美悠、次の『こみパ』っていつだっけ?」
「5月の第3日曜」
即答できるあたり、どうやらそれは遠藤家の恒例行事のようであった。
「そっか、結構先だな」
「父さんの本はでるの?」
「無理そうだって言ってたよ」
「そう、残念ね」
「あ、でも和樹さんは出すんだって」
「お、そりゃ楽しみだな」
ピンポーン
突然鳴り響くチャイムに、会話が中断された。
「私出てくるわね」
そう言って永佳がスタスタと玄関のほうに歩きだした。
「あ、一つ言い忘れてたけどな」
「ん、何?」
「親父のこと、先生って呼んじゃ駄目だからな」
「え、なんで?」
「さあ、あたいにもわかんねーよ。ただ、親父がそう呼ばれるの嫌いみたいだからさ」
「まあ、僕は構わないよ。例えどんな職業でも稔叔父さんは稔叔父さんだしね」
「そっか、そうだよな」
「お父さ〜ん、真紀子さんがいらしたわよ〜」
リビングの中を、永佳のよく通る声が駆け抜けていく。
が、稔が降りてくる気配はなく、そのかわり永佳とその後に続いてキャリアウーマン風の女性が2階へと上がっていった。
・・・・・
第十三話 「服、選択の自由」
「今の人は?」
秋次は椎奈にたずねた。
「澤田真紀子さん。親父が連載してる雑誌の編集長さ」
「……編集長って、直々にくるものなの?」
「さあ、よくわかんねーけどよ。原稿取りに来るのは担当の人みたいだけど、あの編集長も時々うちに来てるぜ」
「ふ〜ん」
暇なんだろうか、と秋次は思った。
が、雑誌の編集長が暇なわけなどなく、今日この家に来たのも新連載に関する細部の打ち合わせのためなのだが、そんな
ことを椎奈も美悠も、ましてや秋次も知るはずはなかった。
「あ、姉貴。真紀子さん何だって?」
階段からスタスタと降りてきた永佳に、椎奈が声をかける。
どうやら、椎奈も真紀子が何をしに来たのか多少気になっているようだ。
「さあ。私もすぐに降りてきたから……」
「そうか」
椎奈との短い会話を済ませた永佳は、紅茶をいれて二階に上がろうとしたが、
「あ、真紀子さん。もう帰るんですか?」
階段の手前で真紀子と出会った。
「ええ、夏樹さんも忙しそうだし、また今度にするわ」
「そうですか。でも、お茶くらい飲んでいったらどうです?」
「ありがとう。でも、これから行かなくちゃいけないところがあるのよ。ゴメンね」
「いえ、いいんですよ。じゃあ、お仕事頑張ってください」
「ありがと。それじゃ」
そう言って真紀子は遠藤家を後にした。
やっぱり忙しそうだ、と秋次は思い直した。
「さてと、明日から学校も始まることだし、今から準備しときますか」
「うん、そうだね」
「え?」
いくらなんでも早いのでは、と秋次は思う。
時刻は午後4時前。
太陽がようやく沈もうとしている時間だ。
学校の準備はその日の朝に済ませる秋次にとって、それは驚くべき早さだった。
「あ、秋次はのんびりしてていいぞ。どうせ、もってくもんなんてないだろうし」
「まあ、そうだけど……ところで、準備って何をするの?」
「服を選ぶのさ」
「服?!」
それは、予想外の答えだった。
「服って、制服があるんじゃ……」
それを聞いて椎奈と、なぜか美悠までもがやれやれといった感じで息をついた。
「あんた、うちの学校のことあんまり分かってないようだね」
「そりゃそうだよ。父さんから急にお前はこの学校に通えって学校の名前聞いただけだし」
「そうか。なら、あたいが簡単に説明しておこう。うちの学校は基本的に服装は自由!よって私服も可」
「え、そうなの?」
「ああ、けど女子で私服を着てるのは少数派だな」
「なんで」
「お姉ちゃんの学校は制服が可愛いの」
「可愛いだけじゃなくて種類も豊富だ。ベースとなる組み合わせだけで24種類もある」
「レパートリーは無限大とも言われてるの」
「しかもその制服を全て無料で提供してる太っ腹さ!!」
「来栖川グループと倉田財閥の共同出資の為せる技だって聞いたことがあるよ」
「よって、前の日に着ていく服を決めとかないと絶対に悩んで遅刻しちまうのさ」
「でも、そのうち段々着る服が決まってくるから不思議なの」
「じゃあ、男子もそんな感じなの?」
怒涛のように喋っていた二人の間をぬって、秋次はそうきいてみた。
「男子の服装は3パターン。学ラン・ブレザー・私服」
「でも、あんまし私服の男の人みかけないよ」
「そういやそうだな。秋次の前の学校はどんな制服だったんだ?」
「一応、ブレザーだけど…」
「なら、それで問題ない。一応、こっちの制服も支給されるだろうけど、無理してそれ着る必要はないぞ」
「うん、わかった」
「というわけで、あたいたちは今から服を見繕う」
「たち、って……美悠ちゃんも?」
すると、美悠は小さく首を横に振った。
「中学は制服決まってるから。お姉ちゃんを手伝うの」
「そうなんだ」
「よし、美悠、行くぞ!」
「おー!!」
何故か気合を入れて出発する椎奈と美悠。
そして椎奈は去り際に、
「覗くなよ☆」
と言い残した。
「……しないって、そんなこと」
「うふふ、若いわね」
「うわぁっ!え、永佳さん、いつからそこに?」
不意にかけられた声に、秋次は過剰に反応してしまった。
見ると、台所で永佳がお茶をすすっていた。
「え?ずっとここに居たわよ」
全然気がつかなかった秋次であった。
「じゃあ、僕も部屋に戻ります」
「夕飯できたら呼ぶわね」
どうやら今日の夕食当番は永佳らしい。
「はい、お願いします」
・・・・・
第十四話 「絶、突き抜ける痛み」
その日の夕方の遠藤家の食卓は、ため息で彩られていた。
「そうか……今日は姉貴の当番だったのか……」
何かを観念したように椎奈が呟く。
美悠に至っては何かに脅えたように体を震わせている。
ちなみに稔は、台所に永佳が立っているのを確認すると、和樹と共に何処かへ出掛けてしまった。
そして、この台所にはあと二人、楽しげに鼻歌など歌っている永佳と何もわからずにキョトンとしている秋次が居た。
秋次の目の前、というよりテーブルの上一杯には綺麗に握られた寿司が、所狭しと置かれている。
「これ、永佳さんが作ったんですか?」
「ええ、そうよ」
いつもの穏やかな笑みで永佳が答える。
「どうしたの、椎奈。何で食べないの?」
「いや、まずお前が食ってくれよ」
ぎこちない笑みで椎奈が秋次に答える。
「美悠ちゃんは?」
その問いに美悠は激しく首を横に振って答えた。
秋次が不思議に思うのも無理はない。
机の上に並べられた寿司は、親に2度ほど連れられた本格的な寿司屋にも負けない見栄えだった。
さらにネタの種類も豊富で、実際、秋次がまだ手をつけていないのは、何から食べようかと迷っていたせいである。
その間にも、永佳はパクパクと寿司を口に運んでいたので、いつまでも手をつけようとしない椎奈と美悠に疑問を感じて
いたのだ。
が、秋次が最初にあたりをつけたハマチを口にいれた瞬間、椎奈たちの行動が理解できた。
「っっっ!!!!!!!!!!」
あわてて何故か手元に置かれていた水を飲み干す秋次。
それでも、まだ、鼻の奥へと突き刺さるような刺激は弱まらない。
そう、この寿司には大量のワサビが含まれていたのだ。
「……永佳さん、これって何かの罰ゲームですか?」
「え?」
ようやく痛みが収まった秋次は永佳に聞いたが、永佳は何事もなかったかのように寿司を頬張り続けている。
「いえ、なんでもないです」
秋次は、これはきっと永佳さんなりのギャグに違いないと思い、今度はイカを口にいれる。
「ぐはっっっ!!!!!!!!!」
そのイカにも、やはり大量のワサビが仕込まれていた。
椎奈と美悠は、そんな秋次を見て両手を合わせて目を閉じていた。
「あら?どうしました?」
かなりオーバーなリアクションをとったせいもあってか、ようやく秋次の方に永佳が目を向ける。
「永佳さん!いくらなんでもワサビ多すぎですって!」
「あら?おいしくないですか?」
詰め寄る秋次に笑顔で返す永佳。
「いや、そういうわけじゃ……」
その笑顔に言い知れぬプレッシャーを感じ、言い淀む秋次。
「そうですか。やっぱり、ワサビはこのくらい入ってないとダメですよね?」
「……ハイ」
そう答えることしか出来なかった秋次は、おのれの無力さを呪った。
「あら?美悠ちゃん、ちゃんと食べてる?」
「う、うん。食べてるよ」
「嘘はダメよ〜。ちゃんと見てたんだから。食べないと大きくなれないわよ〜」
そう言って永佳は美悠の口にイクラを運ぶ。
嫌がるかと思われた美悠であったが、意外にも、すんなりとそれを口に入れた。
それを見ながら秋次は、蛇に睨まれた蛙ってあんな感じなんだろうなあ、などとぼんやりと思っていた。
「椎奈もちゃんと食べてよね〜」
「ハ、ハイ」
何故か直立不動の態勢になった椎奈がおそるおそる手近にあったかっぱ巻を口に入れる。
秋次はそれを見ながら、あれは死んだ魚の目だな、などと思ったりした。
そして、永佳が秋次の方を見ると、秋次は反射的に寿司を口の中に運んでいた。
こうして、この日の夕食はその味を感じることなく終わったのであった……
「……永佳さんの料理って、毎回あれなの?」
寝る前に歯を磨こうと洗面所にやってきた秋次は、先にそこで顔を洗っていた椎奈に尋ねた。
となりでは美悠がうがいをいている。
「まあ、晩飯の時は、な」
なんとなくバツが悪そうに椎奈が答える。
美悠はまだ喉が痛いのか、何度もうがいを続けている。
「どうして永佳さんは平気なんだろう……」
「わかんねえけど、体質なんじゃねえかな。姉貴は激辛全般オッケーみたいだし」
「でも、永佳お姉ちゃん、朝とお昼は普通のお料理作るの」
ようやくうがいを終えた美悠が言った。
「だから、姉貴の晩飯当番は月2回と決まってるんだ」
「ちなみに、今月は?」
「あと一回」
三人は、同時に深いため息をついた。
「ま、姉貴も姉貴なりに秋次を歓迎したかったんだろうよ」
「いつもよりワサビの量多かったもんね」
あまり有り難くない歓迎の仕方だな、と秋次は思ったが、口には出さずにおいた。
「それじゃ、また明日な。お休み、秋次」
「おやすみなさ〜い」
「うん、おやすみ」
二人の後ろ姿を見送った秋次は手早く歯磨きをすませ、自分の部屋へ戻って眠ることにした。
・・・・・
第十五話 「朝、学校への道」
カチッ。
秋次は目覚しが鳴る前にそのスイッチを止めた。
時刻は7時25分。
目覚ましのタイマーは7時30分にセットされていた。
どうやら秋次はこの家での生活に馴染んだらしく、普段の生活リズムを取り戻していた。
「おはようございます」
秋次が階段を降りてダイニングへ向かうと、そこには既に制服姿の椎奈と美悠、スーツを着た永佳が居た。
「おう、おはよう」
「おはよ〜」
「あら、おはようございます」
三者三様の朝の挨拶が返ってくる。
「みんなもう朝ご飯は済んだの?
「ううん、私達も今降りてきたとこなの」
「まあ、今日はトーストとハムエッグだからすぐ出来るさ」
フライパンを巧みに操りながら椎奈が答える。
「ほい、完成と」
そう言って、椎奈は人数分のハムエッグを皿にわけてテーブルに並べ席に座った。
次の瞬間、チン!という音と共にこんがり焼けたトーストがトースターから飛び出してくる。
「それでは、皆さん……」
「いただきま〜す」
4人の声は見事にシンクロしていた。
「う〜ん、まだちょっと時間あるけどそろそろ行くか?」
さっさと朝食を食べ終えてリビングでテレビを見ていた椎奈が言った。
時刻は8時5分。
今日から秋次が通うことになる桜華高校までの距離は、歩いて10分くらいだと秋次は椎奈から聞いていた。
ちなみに、永佳が通う紫苑大学と美悠が通う芙蓉中学も桜華高校と同じ方角にあるが、桜華高校が一番近い。
まあ、3校とも歩いて通える距離にあるわけなので何処も近いといえば近いのだが。
「うん、そうだね。美悠ちゃんはどうする?」
「行く!」
「よし、じゃあ決定だな……って姉貴はまだいいのか?」
椎奈が一人でのんびりと朝刊に目を通している永佳に声をかけた。
「え?ああ、私はこの記事読んだら行くから先に行ってていいわよ」
「……ま、いいけどね。それじゃ、行ってきます!」
こうして、3人は永佳を残して学校へと向かった。
「やっぱちと早すぎたかな?」
学校への道すがら、椎奈はそんなことを呟いた。
今まで5分ほど歩いているのだが、ほとんど誰ともすれ違っていない。
まあ、高校の始業時刻が8時45分なのだから30分ほど前に学校に到着する者のほうが余程珍しいのだが。
「先生も来てなかったりしてな」
「いや、いくらなんでもそれはないんじゃない?」
そんな他愛もない話をしているうちに高校の校門が見えてきた。
「……本当に近いんだね」
前いた学校には自転車で通っていた秋次にとってその近さは驚異的なものであった。
「じゃ、私はここでお別れだね。また後でね〜」
「おう、気をつけてな」
「バイバイ、美悠ちゃん」
大きく手を振って美悠が去っていく。
「さて、あたいたちも行くか」
「そうだね」
「ところで、あたいはクラス分けとか見に掲示板に寄るけど、秋次はどうする?」
「僕はとりあえず職員室に行くよ」
「そっか。職員室は玄関から中に入ったら左に曲がってすぐのとこにあるからすぐ見つかるだろ」
「ありがとう」
「じゃあ、掲示板はあっち側にあるから、ここからは別行動だな」
今まで向かっていたのとは別の方向を指差して椎奈が言った。
「うん、じゃあ」
こうして秋次は椎奈とわかれて一人で職員室へと向かった。
(……って、玄関ってどこだろう?)
秋次は迷っていた。
明らかに道に迷っていた。
秋次は椎奈とわかれた後、今まで進んでいた道を真っ直ぐ歩いた。
すると、校舎に辿りつきはしたけれど、何処にも玄関らしきものが見当たらない。
仕方なく校舎の壁伝いに歩くと入り口らしきものを発見したのでそこから中に入ったが、そこは正面玄関ではなく通用口や
裏口の類だったらしく、正面玄関に普通は設置されている下駄箱もなかったので、しかたなく靴を手に持って秋次は校舎内へ
と入ったのだ。
とりあえずそこから左に曲がってみた秋次であったが、やはりというか職員室は見つからない。
そんな訳で、秋次は校舎内をさまよっていたのである。
人に聞こうにも、こんなに朝早くに学校に来きてる生徒はやはり少ないらしく、何クラスかの教室を覗いて見てもだれも居
なかった。
と、その時、
(人だ!)
秋次の目に今まさに教室に入ろうとする女の子の姿が映った。
「あの、すみません!」
「……何でしょう」
その女の子は扉に伸ばしかけた手を戻し、秋次の方へ向き直った。
「職員室へはどう行けばいいんですか?」
「職員室?」
女の子が怪訝な表情でそう聞いてくる。
「あ、僕、遠藤秋次って言います。今日からこの学校に転校してくることになったんですけど、その、職員室の場所がわか
らなくて……」
何故かしどろもどろになりながら秋次は答えていた。
「そうですか。じゃあ、ついてきてください」
それだけ言うと、少女はスタスタと歩き始めた。
「え?あ、はい」
慌てて後を追う秋次。
職員室へ行くまで、少女は始終無言のままだった。
秋次は何か怒らせるようなことでもしたかな?と思ったが、全く心当たりがない。
それに、こうしてちゃんと職員室へと案内してもらっているので、ますますわけがわからない。
「……着きました」
秋次の頭の中を色々な考えが渦巻いているうちに、どうやら職員室に到着したらしい。
「ありがとうございます。本当、助かりましたよ」
「では、私はこれで……」
「あ、もう一つ聞きたいことがあるのですが……」
立ち去ろうとする少女を秋次は呼び止めていた。
言葉遣いが普段にも増して丁寧になってしまっているのは、目の前の少女が醸し出す雰囲気のせいかもしれない。
「……何をでしょう?」
「あなたの名前です」
そう、秋次はこの少女の名前を知りたかったのだ。
こうして親切に案内してもらったのだから、何かの機会にお礼したいと思い、その為には名前が分かったほうがいいだろうと
思ったのだ。
まあ多少は、少女の事を知りたいという純粋な好奇心もあったのだが。
「……柏木楓」
そう呟くと、楓はスタスタとその場を後にした。
・・・・・
第十六話 「空、降り注ぐ青」
楓の後ろ姿を見送っていた秋次であったが、その姿が見えなくなると急に本来の目的を思い出した。
(そうだ、職員室に入らなきゃ)
そして、控え目なノックの後、職員室の扉を静かに開く。
「失礼します」
礼儀正く挨拶してから職員室に入った秋次であったが、職員室にいる先生もまばらであった。
(って、どこにいけばいいんだろう?)
そう考えてキョロキョロ室内を見回していると、背後から声をかけられた。
「君、もしかして遠藤秋次君?」
「あ、はい、そうですけど」
秋次が振り返ると、そこには教師と思われる女性が立っていた。
「ふう、少し早めに来ておいて正解だったわね」
そう言って、その女性は微笑んだ。
「あの、先生ですよね?」
「ええ、そうよ。あなたの転入するクラスの担任になった常盤沙夜よ。これからよろしくね」
「あ、はい。こちらこそ」
「さてと、そろそろ始業式はじまるわね。あ、あなたはホームルームからでいいから、ここで待っててくれる?」
「ここって、職員室でですか?」
正直な話、職員室というのは余り居心地のいいものではない。
秋次には別段やましいことはないが、あまり長居したいとは思わない場所である。
「う〜ん、やっぱりそれじゃ退屈よね。じゃあ、校舎見学でもしてていいわよ」
「はい、そうします」
「ただし、始業式が終わるまでにはここに居ること。わかった?」
「はい」
「うむ、よろしい」
そう言って沙夜は職員室を後にした。
しばらくして、チャイムが聞こえてくる。
どうやら始業式が始まったようだ。
「さて、と」
そう一言呟いて、秋次も誰もいなくなった職員室を後にした。
(……柏木、楓さんか……)
秋次は校舎内を歩きながら、なんとはなしに先ほど出会った少女の事を考えていた。
楓は、独特の雰囲気を持つ少女であった。
誰も近づけないようで、どことなく儚げで、けれどはっきりとした意思の瞳を持つ少女。
名前だけは聞いたけれど、もう一度会えるかどうかもわからない。
けれど秋次はなんとなく予感していた。
その少女との再会を。
そして秋次は、何時の間にか屋上へと続く階段の前で立ち止まっていた。
(……いつ階段を上ったんだ?)
楓のことを考えていたせいか、ここまでの道のりが余り思い出せない。
それでもここまで来たのだからと屋上へと出てみることにする。
立ち入り禁止の看板などがない事から、どうやらこの学校は屋上へは自由に行き来できるらしい。
そして、秋次が屋上への扉を開けると、そこに先客がいた。
「あ〜、始業式さぼっちゃいけないよ」
「え?!」
「って、私もだけどね」
てへ、っといった感じで秋次の目の前の少女が微笑む。
「はじめまして、だよね?」
「え、ええ」
「私は川名みさき。今日から3年生になるの」
「川名……先輩」
「あ、みさきでいいよ」
「じゃあ、みさき先輩」
「うん。で、君は?」
「え?」
「名前。君の名前も教えて欲しいな」
「あ、僕は2年の遠藤秋次です」
「ふ〜ん、秋次君か。で、どうして秋次君は始業式を抜け出してこんなとこに居るのかな?」
悪戯な笑みをうかべてみさきが聞いてくる。
「え、いや僕は別に抜け出したとかそういうんじゃなくて、えっとその……」
みさきにペースを乱されたのか、しどろもどろになりながらも秋次が答えようとすると、
「ふふふふっ」
と、みさきの笑い声が聞こえてきた。
「え?」
「秋次君って面白いね」
「え、いや、はあ」
秋次は何と答えていいかわからずに、曖昧にそう口にした。
「私はね、風を感じにきたんだ」
「風?」
その、今までとはうって変わった真剣な口調に、秋次はハッとしてみさきの顔を見つめた。
そしてようやく気づく。
みさきの瞳が、光を宿していないことに。
「みさき先輩……もしかして、目が……」
「そう。私は目が見えないの」
なんのためらいもなくみさきが答える。
「どうやってここへ?」
秋次があたりを見回しても、屋上に二人以外の人影は見当たらない。
それに、みさきは盲目の人が持つような杖も持っていなかった。
「もう、慣れたからね」
「だからって、危ないんじゃ……」
「秋次君。私はね、特別扱いされるのってあんまり好きじゃないの。ただちょっと目が見えないだけの女の子、そう思って
ほしいんだ」
それは、とても強い声だった。
「それにね、感じることは出来るのよ。だから、私はこうやって風を感じてるの」
そう言って両手を広げるみさき。
その姿はとても神秘的に見えた。
「……みさき先輩は、強いんですね」
秋次は心からそう思った。
そして、出来るだけみさきとは自然に接しようと心に決めた。
「まあ、確かに体は丈夫だけどね」
微笑むみさき。
「だからって、始業式さぼったらダメですよ」
「あら?それは秋次君も一緒じゃないの?」
「いや、僕は今日からこの学校に転入するんです。だからホームルームまでは学校の見学してていいって。ちゃんと担任の
許可もとってます」
「なんだ、そうだったのか。ちょっと残念だな〜、お仲間が増えたと思ったのに」
そう言ってみさきは微笑んだ。
「あ、チャイム」
「そろそろ始業式終わったみたいだね」
そう言ってみさきはゆっくりと歩き出す。
「さて、私たちも戻ろうか」
「そうですね。……ところでみさき先輩」
「ん、何?」
「職員室の場所ってわかりますか?」
こうして、みさきに連れられた秋次はなんとか職員室にたどりついたのであった。
・・・・・
第十七話 「室、訪れた空間」
「もう、ちゃんと時間までには帰ってきとかなきゃ駄目でしょ」
そう言う割には、沙夜の口調は穏やかだった。
「はい」
「あんまり時間にルーズだと女の子に嫌われるわよ」
「はあ」
「まあ、慣れてないんだから仕方ないわね。じゃあ、行くわよ」
そういって歩き出す沙夜の後に秋次はついていった。
「ここがあなたの教室よ」
沙夜が立ち止まった場所に、秋次はなんとなく見覚えがあった。
まあ、学校の教室なんてどこも同じような作りなのでそう思えただけかもしれないが。
扉の上にあるプレートには「2−B」と記されていた。
「じゃあ、先生が呼んだら入ってきてね」
「はい」
沙夜が教室の扉を開けると、今まで喧騒が渦巻いていた室内が静かになった。
「はい、みんな席に着いて〜」
沙夜のよく通る声が室内に響き渡る。
その声は廊下にいる秋次にもはっきりと聞こえてきた。
「さて、私がこのクラスを受け持つことになった常盤沙夜よ。まあ、結構知った顔もあるけどこれからよろしくね」
一斉に湧く教室。
「はいはい。で、早速だけど嬉しいニュースがあります。新学期早々、うちのクラスに新しい仲間が増えることになりました」
おおっ、とどよめく室内。
「先生!女の子ですか?!」
そしてお決まりの質問を投げかける男子生徒。
「残念。男子よ」
その瞬間、教室の騒音が半減した。
「……現金ね、君たち。まあ、いいわ。遠藤君!入っていいわよ」
沙夜に呼ばれるまま、秋次は教室の扉に手をかけた。
ただ、何分転校など始めての経験なので、少し緊張してうまく力が入らず、なかなか扉が開かなかった。
そして、なんとか扉を開いた秋次であったが、その緊張はさらに増していた。
しかし──
教室に入った瞬間、秋次の緊張は何処かへと飛んでいった。
教室には、秋次の知った顔があったのだ。
しかも、四人も。
遠藤椎奈、藤田浩之、月宮あゆ、そして柏木楓。
それらの顔が秋次の目に飛び込んできた為に、秋次は平常心を取り戻していた。
秋次の耳には、
「やっぱり秋次だったのか」
「ふ〜ん、お前知ってたのか?」
「わぁ、秋次くんだぁ」
と語りあっている友人たちの声が聞こえてくる。
ただ、楓だけは何の反応も示さず秋次を見ていただけであった。
「さあ、遠藤君。みんなに挨拶して」
「あ、はい。えっと、今日からこの学校に通うことになった遠藤秋次です。みなさん、よろしくお願いします」
自分でもあたり障りの無い普通の挨拶だなと思いつつ、秋次は頭をぺこりと下げた。
「……不合格ね」
「え?」
不意に告げられたその言葉にただ驚く秋次。
そして、それが沙夜の言葉だったことに気づきさらに驚く。
「せ、先生?」
「遠野さん!」
秋次の疑問を制するように、沙夜が誰かを呼んだ。
「……はい」
すると、教室の後ろの方に座っていた一人の女子生徒が静かに立ちあがり、秋次の方へとやってきた。
「これを……差し上げます」
「え、あ、これは?」
「残念賞です」
その少女、遠野美凪が差し出したのは白い封筒で、その表面にははっきりと「進呈」という二文字が記されている。
「あ、どうも」
その封筒を反射的に受け取る秋次。
すると美凪は満足そうに自分の席へと戻っていった。
(一体なんなんだ?)
と思いながらも一応中身を確認する秋次。
(……お米券?)
謎は、さらに深まった。
「さて、お約束も済んだところでもう一度やり直しよ」
「え、あの……」
「いい?第一印象って大事なのよ?これを成功させないことには、あなたには未来永劫明るいスクールライフはやってこない
と思いなさい!」
「あ、は、はい」
沙夜のあまりの迫力に、つい返事をしてしまった秋次であったが、これといっていい挨拶など浮かばない。
(ええい、ままよ)
しかし、ついに腹をくくった秋次は精一杯自己アピールしてみることにした。
「クケェーーーーッ!!!!」
静まり返る室内。
(しまった、『ニョローーーッ!!』の方がよかったか?)
そんな見当違いの反省をしている秋次だったが、
「合格」
と、意外にも沙夜からのオーケーサインが出た。
「ただし、学級崩壊だけはさせないでね」
という条件つきではあったが。
「それじゃあ、遠藤君の席だけど……神尾さんの隣が空いてるわね。あそこに座ってちょうだい」
「えっと、あの窓際の席ですね。わかりました」
そう言って秋次はその席の方へと歩き出した。
途中、椎奈や浩之に挨拶についてつっこまれながらも、なんとか席にたどりついて座る。
すると、
「にはは。お隣さんだね」
と、秋次の隣に座っていた少女が話しかけてきた。
「え〜と、神尾さん?」
「うん。私は神尾観鈴。これから隣同志、仲良くしようね。にはは」
「うん、こちらこそ」
「でね、さっきの挨拶だけど『がおーー』の方が良かったと思うんだ」
「がおーー?」
「そう、がおーー」
「お前ら、さっきから何がおがお吠えてるんだ?」
突然、秋次の後ろの席から声がかけられた。
「が、がお…」
「あ、ごめん。うるさかった?」
「いや、まあ別にいいんだけどな。ところでお前って……変なやつだな」
「祐一!いきなり変な奴って言うのは失礼だよ」
今度は、秋次の後ろに座っている男子生徒、相沢祐一の隣の席の女子生徒が会話に割って入ってきた。
「ごめんね、遠藤君。祐一も悪気があって言ったわけじゃないと思うんだ」
「あ、別に気にしてないからいいよ。それに、実際たまに言われるからね、変な奴って。あ、え〜と……」
「あ、私は水瀬名雪。で、こっちが相沢祐一だよ」
「えっと、水瀬さんと相沢君だね」
「俺のことは名前でいいぜ。その方が気楽でいいし」
「私も名前でいいよ」
「私もー私もー」
すっかり会話の輪から外されてしまっていた観鈴が舞い戻ってくる。
「じゃあ、僕のことも名前で呼んでいいよ。祐一君、名雪ちゃん、観鈴ちゃん」
「あ、俺は呼び捨てにしてくれて構わないぞ。っていうか、そうしてくれ」
「うん、わかったよ。祐一」
こうして、クラスにいつのまにか溶けこんでいく秋次なのであった。
・・・・・
第十八話 「決、選択の余地」
「はい、それじゃあホームルームを再開するわよ」
秋次の紹介も終わり室内が騒然とし始める中、沙夜が喧騒にも負けないよく通る声で話し始めた。
「といっても、今日はクラス委員を決めるくらいなんだけど……」
そう言って沙夜は教室を見回す。
と、その視線がピタリと一人の少女を捕らえた。
「そこのおさげに眼鏡のあなた!え〜と」
沙夜は視線を落して名簿を確認している。
このクラスは特に出席番号順に座ってるというわけではないのだが、沙夜の持つ名簿には2−Bの生徒全員の顔写真が貼って
あるのだ。
もっとも、沙夜は昨年もこの学年の国語の授業を受け持っていたので、大体の生徒の顔はわかるのだが。
どうやら、名前と一致させるのは苦手なようだ。
「……保科智子さんね?」
「そうですけど。うちが何か?」
智子は怪訝な表情で沙夜を見返している。
「あなた委員長顔ね。というわけで、クラス委員に決定!」
「な?!」
「そんなの横暴だと思います!」
ダン!と音をたてて立ちあがったのは、指名された智子ではなく、その隣に座っていた少女だった。
「あなた……ええと、太田香奈子さんね」
すかさず、名簿で名前を確認する沙夜。
「先生、そんな理由で委員長を決めてもいいんですか?ね、保科さんもそう思うわよね?」
「ま、まあ」
完全に香奈子の気迫に押された智子が曖昧に頷く。
「でも、『クラス委員になりたい人は立候補してください』っていったって、別に誰も名乗りでないでしょ?だったらこっち
で勝手に決めた方が効率がいいじゃない」
確かに、クラス委員になっても特典があるわけでもなく、自分からなりたがる者は少ないだろう。
そう、少ないだけであっていないわけではないのだ。
「わたしが立候補します」
香奈子のその言葉に教室がざわめく。
「あなた、本気?」
「本気と書いて、マジです」
おちゃらけた言葉とは裏腹な鋭い眼差しが沙夜を捉える。
「……ふぅ、わかったわ。まあ、断る理由もないしね。それじゃあ、太田さん、委員長になってちょうだい」
「任せてください」
教室内にワーっと拍手がわきおこる。
「じゃあ、次に副委員長だけど、委員長、あなたが選んでいいわよ」
「嫌です」
その言葉に、思わず前のめりになる沙夜。
「あ、あなたねえ…」
「だって、それってさっき先生がやろうとしたことと一緒じゃないですか」
「まあ、それはそうだけど…じゃあ、だれか立候補する人、いる?」
一応、といった感じで沙夜がクラス中を見渡す。
しかし、やはりというか案の定というか、立候補者は見当たらない。
「普通そうよね…」
ぽつりと沙夜が呟く。
「で、こういった場合次はどうするの?」
「自薦がなければ他薦でいいから、この人が適任だって人を推薦してください!」
すっかり場をしきっている香奈子である。
(さすがに立候補しただけのことはあるわね)
などと沙夜が心密かに思っていると、一人の女子生徒の手が挙がった。
「先生、彼女の名前は?」
小声で香奈子が聞いてくる。
「え〜と……この娘ね。髪型変えたみたいだけど、神岸あかりさんで間違いないわ」
小声で沙夜も答える。
「はい、神岸さん、どうぞ」
名前を呼ばれて少し驚いたようなあかりだったが、ゆっくりと椅子から立ちあがった。
「え〜と、私は保科さんが副委員長に適任だと思います。私は1年の時も保科さんと同じクラスだったから、保科さんの
委員長ぶりはしっかりとこの目に焼きついています」
「あかりちゃん、日本語ちょっと変だよ」
隣の席に座っていた佐藤雅史が小声でなにやらつっこんでいる。
「というわけで保科さんに清き一票をよろしくお願いします!」
最後のほうは完全にパニックに陥っていたあかりであった。
「なにやってんだか」
遠くで浩之がためいきをついている。
実は、浩之があかりに智子を推薦させたのだが、そのことには誰も気づいていないようだ。
それでも、浩之の目論見は成功したといえる。
「どうします?保科さんはこの推薦を受けますか?」
香奈子が智子に尋ねた。
どうやら香奈子は個人の意思を尊重するタイプのようだ。
「……しゃーないな。乗りかかった船や。やってええよ」
またもおお、とどよめく教室。続いて拍手の嵐。
基本的にこのクラスの生徒はノリがいいようだ。
「じゃあ、決まりね。じゃあ改めて自己紹介してもらうから太田さんと保科さんは前に出てきて」
言われて前に出て行く二人。
「じゃあ、委員長からどうぞ」
「はい。この度委員長を任された太田香奈子です。去年は1−Dでした。初対面の人が多いと思うので、これからよろしく
お願いします」
ペコリ、と頭を下げる香奈子。
どっと拍手がおこる。
「じゃあ、次。副委員長」
「え〜、なんやらなりゆきって感じで副委員長になってもうた保科智子です。去年は1−Aでした。いたらんとこもある思
いますが、大目に見たってください」
深々と頭を下げる智子。
また、拍手。
「はい、どうもありがとう。二人とも席に戻っていいわよ。……さて、今日のホームルームはこれで終わりね。あとはさっ
さと家に帰るなり教室に残って喋るなり、あなたたちの自由にしていいわよ。じゃあ、委員長、号令よろしく」
「起立!気をつけ!礼!」
妙に張りきった香奈子の号令でこの日のHRは終了した。
・・・・・
第十九話 「迎、未来への回帰」
「さて、これからどうするよ?」
HRが終わってすぐに、秋次の周りに出来た輪の中で、まず浩之がそう口にした。
「やっぱ歓迎会しかないっしょ」
椎奈が、さも当然というように言う。
「じゃあ、たい焼きパーティーだね!」
「あゆはちょっと黙ってろ」
「うぐぅ」
あゆの突飛な提案を、祐一が即座に却下する。
「たい焼きはちょっとあれだけど、どこかでご飯っていうのが妥当なんじゃないかな」
というのがあかりの提案。
「うん、そうだね」
それに同意する名雪。
「それから、あとはカラオケで決まりね」
いつの間に輪の中に入っていたのだろうか、ひょっこり現れた志保が口を開く。
「あ、いや、僕は歌はちょっと……」
いままで周りのパワーに押されまくっていた秋次が、かろうじて自分の意見を口にした。
「そうなの?じゃあ今回は許してあげましょう」
何故か偉そうな志保。
「んじゃとりあえずどこ食いに行くか決めるか」
「あ、ちなみに『HONEY BEE』には昨日連れていったから」
「ふむ。なら『HONEY BEE』は選択肢から外すとして、残るは『百花亭』かレミィがバイトしてるファミレスか……お、レミィ
丁度いいところに」
「What?なに、ヒロユキ」
浩之はたまたま教室に入ってきたブロンドの少女、宮内レミィを呼び止めた。
彼女は、見た目どおりのハーフである。
「レミィ、今日バイトは?」
「Um〜、お休みだけド?」
「そっか、じゃあ皆で『Curio』に行こうぜ」
「待て藤田。今日は月曜日。確か『Curio』は定休日のはずだ」
「Yes!だから今日はお休みネ。それにしてもユーイチ、よく知ってたネ」
「まあ、ちょくちょく通ってるからな」
「しょっちゅうの間違いなんじゃないの?」
顔をにたにたさせながら、志保が祐一に詰め寄る。
「まあ、あそこには男の浪漫が溢れてるからその気持ちもわからんではないが」
「ってか、はやいとこどこ食べに行くか決めよーや」
話の収拾がつかなくなりかけた時、椎奈が話を本線に戻す。
「んじゃ、近いし『百花亭』で秋次の歓迎会ってことでいいかな?」
「おおー」
そして教室を後にする、秋次・椎奈・浩之・あかり・レミィ・志保・祐一・名雪・あゆの一行。
秋次は去り際に、楓の席をちらりと見た。
そこには、既に楓の姿はなかった。
「どう思う、万葉?」
「間違いない、みたいね」
秋次の席の喧騒からやや離れた位置に、顔を向き合わせて囁きあう男女の姿があった。
その視線は決して秋次たちの方に向けられなかったが、彼らには全ての動向が把握できていた。
「それで、武はどうするの?」
「今は、まだ様子を見よう。ここには、不確定な要素が多すぎる」
ちらり、と横に視線を向ける。
そこには、今だに爆睡を続ける男子生徒と、それを必死で叩き起こしている女子生徒の姿があった。
「そうね」
彼女もちらりと視線を扉へ向ける。
そこにも、今まさに教室を去ろうとする男女の姿があった。
「これは偶然かしら?」
「これを偶然と思えるほど、俺はお目出度くはないつもりだが……必然にしては出来すぎている」
「そうよね」
ふう、とため息をつく。
「彼らは、気づいているのかしら」
「那須宗一、月島瑠璃子、そして柏木楓。この三人は確実に気づいているだろう」
「私たちのことも?」
「ああ、まず間違いない」
「まったく、やりにくいわね」
「いや、逆に好都合かもしれないぞ」
「え?」
「たけちゃ〜ん、一緒に帰ろ」
万葉の疑問は、扉から教室に入ってきた少女によってかき消された。
「ん、栞。お前のクラスもHR終わったのか?」
「うん、今終わったよ」
「あれ、栞のクラスって2−Dでしょ。担任って確か青柳先生よね?珍しいわね、HRが長引くなんて」
「それがねー、なんかゴタゴタしちゃってて千歳ちゃんじゃ収拾つかなくなっちゃったんだよ。そしたらたまたま通りかかった
常盤先生と香月先生がなんとかしてくれて一件落着って感じだったかな」
「なんだ、栞のとこは栞のとこで大変そうだな」
「本当だよ。これから毎日わくわくどきどきだよ」
「俺としては平穏無事に過ごしたかったんだがな」
栞の少し後に教室に入ってきた男子が、武たちに近づきながらかったるそうに呟く。
「あ、汰一くんもD組だったっけ?」
「ああ。それでうちのクラスにも武ってのがいるんだが」
「白銀武か?」
「ん?なんで知ってるんだ?」
「いや、一年の時同じクラスだったしな。名前が同じだったのもあって仲は意外と良いぞ」
「まあ、そんなミニ情報はどうでもいいとして。その武を追ってきた女が居るんだ」
「なんだ、あいつも意外と甲斐性があるな」
「名前は御剣冥夜」
「御剣………って、まさか、あの御剣グループの?」
「そう。そのまさかだ」
それを聞いて、はぁと頭を抱える武。
「倉田財閥、来栖川重工に続いて御剣グループまで?なんで日本、いや世界三大企業の令嬢がこの学校に集まってるんだ?」
「これも、彼の影響かしらね」
「いや、ここまでくるともう要因が一つと考えるのは危険だろう。実際、御剣は完全なイレギュラーだ」
「ねーねー、何の話?」
「いやなに、大人の話だ」
「ぶー、たけちゃんはそうやっていつも人を子供扱いするんだから」
「実際子供だろ、お前。それはそうと、そろそろ帰るか」
「ええ、そうね」
ぶーぶー文句を言い続ける栞を無視して、武は席から立ち上がった。
(なんにせよ、遠藤秋次。彼には注意を払う必要がある)
これは、武の心の声。
そして、それを拾えるのは、万葉のみ。
(そうね。私たちと同じ、特異点か。あるいは、中和者か)
(後者であることを願いたいものだが)
(いずれにしろ、まだ見守ることしかできないわね)
(ああ、果たしてこれから何が始まるのか。それとも、何かが終わるのか)
・・・・・
第二十話 「序、萌芽の予兆」
「いらっしゃいませ、何名様……ってなんだ、祐一か」
秋次たちが店内に入った時案内にやってきた店員は、何故か祐一を見ると嫌そうな顔をした。
「おい真琴、客に対してそんな態度とっていいと思ってるのか?」
「ん?だって祐一だし」
「祐一だけじゃないよ、私もいるよ」
「というか真面目に仕事しろ、真琴。とりあえず9名だが空いてる席はあるか?」
「奥の座敷が空いてると思うから勝手に座っとけば?」
「だから真面目にやれと言ってるだろう………よし、宮内」
「What?」
急に話を振られて驚くレミィ。
「こいつに手本を見せてやってくれ」
そう言って真琴の頭をぐりぐりと押さえる祐一。
「あぅ〜」
「まぁ、別に構わないケド。あんまり手本にはならいと思うネ」
「レミィがバイトやってるとこって特殊だからねぇ」
「うんうん」
頷きあう志保とあかり。
「特殊って、どんな風に?」
秋次は帰りがけの会話でレミィがファミレスでバイトしていることは知っていた。
だから、ファミレスのマニュアルはどこも似たようなものだと思っている秋次にとって、特殊とはどんなものか全く想像がつか
ないのである。
「まあ、見てればわかるさ」
何故か含みのある笑みを浮かべて、浩之が囁きかけてくる。
「う、うん」
「それではレミィ教授、はりきってどうぞ〜」
いつのまにか場をしきっていた志保がレミィを促す。
すると、レミィは秋次たちの方にくるりと向き直ると
「お帰りなさいませ、御主人様」
と、はじける笑顔で頭を下げた。
「な……」
その挨拶に秋次は度肝を抜かれたが、他のメンバーは大して動揺もしていない。
そしてレミィはそのまま、なぜか秋次たちを奥の座敷へと案内し始めた。
「あぅ〜、それ私の仕事……」
「で、さっきのあれって何だったの?」
座敷に座り、めいめいの注文が終わったところで秋次がレミィに尋ねる。
「あれは、私がアルバイトしてる『Curio』風の接客ネ」
「『Curio』っていうのは、中世欧州風の雰囲気を醸し出してるファミレスなんだ。まあ、ファミレスというか喫茶店に近いけ
ど。で、そこのウェイトレスはメイド服を着てて、男性客を『旦那様』女性客を『奥様』と見なしてるんだと。そして『Curio』
は旦那様と奥様の家。だから入店時は“お帰りなさいませ”で帰る時には“行ってらっしゃいませ”って言うんだ」
「へぇ。でも、なんで椎奈がそんなに詳しく知ってるの?」
「ああ、去年の夏休みあそこでバイトしてたんだよ。一号店は学生は雇ってくれないんだけど、今レミィも働いてる二号店はま
だ出来たばっかで人手不足だから学生でも雇ってくれるんだ」
「店長の趣味って話もあるけどねー」
「でも、いっつも思ってたんだけど、なんでレミィだけ『御主人様』なの?」
誰もが抱いている疑問を代弁するあかり。
「だって、メイドと言えば御主人様だヨ?」
そして何の疑問もなく言ってのけるレミィ。
「それは、店のポリシーに反するんじゃないの?」
秋次がそう言うと、
「Why?店長もこっちのほうがイイって言ってたヨ?」
「………それは明らかに店長の趣味だな………」
「そうだね……」
「まあ、レミィが気にしてないなら別にいいんじゃない?それより料理ちょっと遅くない?」
「混んでるんだからしょうがないよ」
あかりが言うように、店内は既に飽和状態であった。
そして、女子の制服が千差万別なので一見するとわからないが、客の半数以上があかり達と同じ桜華高校の生徒なのである。
そうこうしているうちに各自の料理が届けられる。
「それでは皆様お手を拝借」
「志保〜、それってちょっと違うと思うよ」
「気にしない気にしない。それでは本日の主賓・遠藤秋次くんから一言お願いします」
「え、ぼ、僕?」
「そりゃそうよ、なんてったってあんたの歓迎会なんだから」
「まあ志保は騒げればなんでもいいんだろうけどな」
「確かにね」
「ちょっと、浩之!あかり!何失礼なこと言ってるのよ。そんなこと言うとあんたたちの恥ずかしい過去をこの場で暴露しちゃ
うわよ?」
「ゴメンなさい」
息もぴったりに謝る浩之&あかり。
「まあ、それはそれとして。秋次、なんかやんなよ」
「なんかって言われても……」
こういう場に慣れていない秋次はおろおろするばかりだ。
「普通でいい?」
「却下」
どうやら皆さん何かを求めているようだ。
(ええい、ままよ!)
「一番、遠藤秋次!脱ぎます!!」
「まて、早まるな!なんで下からなんだ?!」
「秋次くんって意外と大胆なんだね…」
「というか、あれはどうみてもヤケだろ」
「離せ!僕はNo.1になるんだ!」
「殿、殿中でござる、殿中でござる!」
「ま、楽しそうだしいいんじゃない?」
「それじゃ余興もすんだことだしそろそろ食べましょうか」
「そうだね、それじゃ、いっただっきまーす」
「いっただっきまーす」
「はっ!僕は一体何を………?」
「秋次、グッジョブ」
ぐっと親指を突き立てる祐一。
「秋次くんも早く食べようよー」
「え、あ、うん」
あゆに促されて、やっと皆が食事を始めていることに気づく秋次だった。
「そういえば、詳しい自己紹介がまだだったわね」
みなが食事を終えた後、志保がそう呟いた。
「そうは言うが、なんだかんだいっても皆知った顔だぞ。あ、そうか秋次とは初対面のやつが多いのか」
そう言って納得する浩之。
「なんか秋次って昨日今日会ったような気がしないんだよなぁ……なんでだろ」
「いや、僕に聞かれても…」
「というわけでまずは私、長岡志保からいっくわよー。スリーサイズその他の個人情報はトップシークレット!でも他人の情報
はなんでもお任せ。歌って踊れる学園のアイドル候補生、長岡志保、長岡志保をよろしくお願いします!」
「まあ、ただ騒がしいだけで別に害はないと思うからそんなに怯えるな。ちなみに志保はA組で俺らとは別のクラスになる」
「私と浩之ちゃんと同じ中学出身なんだよ」
志保の情報に追加をする浩之&あかり。
「そゆこと。じゃ次は浩之とあかりね」
「1セットにするなっつーに。じゃ、まずは俺からな。名前は藤田浩之。趣味は寝ること。以上」
「もう、浩之ちゃん真面目にやってよー。あ、私は神岸あかり。趣味は料理かな?浩之ちゃんとは家が近所で、ちっちゃい頃か
ら一緒に遊んでるんだよ」
「補足その1〜。時々仕草がおばさんくさい」
「補足その2〜。くまグッズマニア」
「もう、変なこと言わないでよ」
浩之&志保の補足に言い返すあかり。
しかし、顔は笑っていた。
「次は私ネ。名前は宮内レミィ。クラスはC組で皆と違うのが残念ネ。パパがアメリカ人、ママが日本人のハーフです。趣味は
Hunt!」
そう言って銃を構える真似をするレミィ。
「なんか、過激な趣味だね……」
「ま、弓持ってなきゃ安全なんで安心しろ」
ということは弓を持つと危険なのかと思った秋次だが、あえて深く聞くのはやめておいた。
「次は俺な。名前は相沢祐一。趣味は寝ること。以上」
「祐一!それじゃ藤田君と一緒だよ!」
「いや、繰り返しは基本だろ?」
「うぐぅ、祐一くん、何の基本かわからないよ」
「ちっ、しゃぁねえなぁ。んじゃもうちょっと詳しくやってやるか。とりあえず、こっちには去年の3学期に引っ越してきた。
引越しとは言っても俺だけこっちに来たんで、こいつん家に同居してるんだがな」
と言って名雪の髪をくしゃくしゃ撫でる祐一。
「もう、やめてよ祐一〜」
「ちなみに、さっき俺たちを案内しようとしてた女の子、沢渡真琴っていうんだが、あいつも俺たちと同居してる。まあ、あい
つの場合同居っていうより居候だけどな」
「祐一も同じようなもんだよ」
「うっさい」
「うぐぅ、祐一くん、それ、ボクの頭……」
「ほれ、次、次」
「うん、わかったよ。私は水瀬名雪。好きな食べ物はイチゴだおー。好きな動物はネコだおー」
「でも猫アレルギーなんだよな」
「うん、だから触れないんだおー」
「そして私が月宮あゆ。好きな食べ物はたい焼き!すきな動物はたい焼き!」
「いや、それ動物じゃないっしょ」
瞬時に椎奈のツッコミが入る。
「うぐぅ…」
「じゃ、最後はあたいだね。遠藤椎奈。秋次とは従兄弟同士ってことで一緒に暮らすことになったんだ。というわけで不束者で
すがよろしくお願いします」
「…………え?」
突然ペコリと頭を下げられて困惑する秋次。
「あー、あんまり気にするな。椎奈は昔から改まった挨拶っていうのが苦手なんだよ」
苦笑しながら浩之がいう。
「はぁ、まぁ、こちらこそ」
それでも律儀に返事を返す秋次であった。
こうして自己紹介は終わったものの、その後も他愛ないおしゃべりが続いて。
「さて、ぼちぼち帰るとしますか」
と、志保が言った時には店内の客は既に数えるほどしか居なくなっていた。
「あれ、真琴、どうしたんだ着替えて。もしや、バイト首になったのか?」
「バッカじゃない?私は仕事あがったの。にしても祐一たち、一体ここに何時間居ると思ってるのよ」
「結構長く居たからなぁ。3時間くらいか?」
「ハズレ。6時間よ6時間!よく飽きないわよね」
はぁとため息をつく真琴。
「じゃ、私は先に帰るから。秋子さんにはもうすぐ祐一たちも帰ってくるって言っておくわ」
「ああ、悪ぃな」
「にしても6時間はちょっと長居しすぎたんじゃない?」
「大丈夫よ、過去に16時間という最長不倒を成し遂げたことがあるから」
「さすがにあの店にはあれ以降行ってないけどな」
なにやら後ろで不穏な会話がなされているのに気づかない振りをして、自分の会計を済ませた秋次は外にでた。
外は既に、夕暮れの狭間の空模様を醸し出している。
「まだ、ちょっと暗くなるのが早いな」
「そうだね」
並んで空を見上げる秋次と椎奈。
「そんじゃあ二次会にれっつごー!!」
全員が外に出たところで、志保が意気揚々と叫ぶ。
「あ、悪い。秋子さん待ってるだろうから俺パス」
「私も」
「うぐぅ、ボクも帰らないと」
「俺は別に構わんが、あかりとレミィはどうする?」
「ゴメン、今日はパパたちと食べる約束なの」
「私も、お母さんもうご飯作ってると思うし」
「それじゃ、秋次と椎奈は?」
「あたいたちは別に………って、ああ!今日あたいの晩飯当番の日じゃないか!というわけで志保、ゴメン!秋次、急ぐぞ!!」
「え、え、ええ〜〜〜??」
風のように立ち去る椎奈に連れ去られる秋次。
「むう、主賓が消えたんじゃ今日はもう解散ね」
「そうだな」
「それじゃ皆また明日〜。風ひくなよ〜」
「風呂入れよ〜」
「宿題しろよ〜」
などとふざけあいながら別れる一同であった。
一方その頃の遠藤家。
「椎奈お姉ちゃん、ちょっと遅いね」
「そうねぇ。私が作っちゃおうかしら?」
それを聞いた美悠はびくっと身体を硬直させ、ふるふると首を横に振った。
「冗談よ。材料もないし」
ほっと胸を撫で下ろす美悠。
「おや、椎奈はまだ帰ってきてないのかい?」
すると、二階から稔が降りてきた。
「父さん、今日は早いわね」
「ああ、ちょうど原稿の目処がたったんでね」
「パパ、お腹すいた…」
「そうだな、たまには出前を取るのもいいだろう」
「待った!出前待った!」
そこに、急いで戻ってきた椎奈が現れた。
その手に買い物袋が握られていることから、夕飯の材料も買ってきたようだ。
ちなみに、もう片方の手には瀕死の秋次がぶらさがっていた。
「椎奈、速過ぎ……」
「んだよ、男のくせにだらしねーなー。んじゃ、ちゃっちゃと飯作るから親父たちはその場で待機!」
そう言い残してキッチンに向かう椎奈。
「災難だったわね、秋次さん。でも、なんでこんなに遅くなったの?」
「いや、学校の帰りに僕の歓迎会をやってもらってたんで、それで」
「そう、それなら仕方ないわね」
「あいよ、お待ち!」
「速っ!もう作ったの?」
秋次の目の前に出された料理はカツ丼。
カツがこんなに速くあがるのか甚だ疑問ではあったが、見栄えは美味しそうな色をしていた。
「当たり前だ。あたいの料理は“速い、安い、それなりの味”がモットーだかんな」
「あの、最後の“それなりの味”ってのがそこはかとなく気になるんですけど」
「まあ、食ってみりゃわかる」
言われるまま、秋次はカツ丼を口に入れる。
別段不味いというわけではない。
かといって、美味いと褒めたくなるような味でもない、いたって普通の味わい。
「……それなりの味だね」
「な。もともとこの周りには美味い店がゴロゴロ転がってるからな。たまにはこういうのも食わないと舌が麻痺しちまうぞ」
「確かに、椎奈の料理食べると妙に落ち着くのよね」
コクコクと頷く美悠。
「椎奈の料理は一番恵都の味に忠実だからね。もっとも、椎奈は意識してこういう味を出してるけど、恵都はこういう味しか出
せないからね」
といって、ははと笑う稔。
「そうなの?」
「ああ、あたいは作ろうと思えば美味しいもんだって作れるさ。時間はかかるけどな」
「その辺は父さんに似てるのよね」
「ところで、秋次は料理とか出来るのか?」
「全くダメ」
「ま、そりゃそうか。となると洗濯……は色々とマズイか。じゃあとりあえず風呂掃除くらい週一でやってもらうからな」
「うん、それは構わないけど」
「というわけでだ、秋次はもうお客様じゃなくてあたいたちの家族なんだから色々と手伝ってもらう」
「そうね、色々と男手があると便利だし」
「お、お手柔らかに……」
それにしても、と秋次は思う。
(家族、か)
白々しい言葉だが、やはり、どこか温かい。
そして、懐かしかった。
父も母も健在だが、元々海外を飛び回っていることが多かったために、あまり家族の繋がりというものを感じたことはなかった。
それでも家族の温かさを知っていたのは、両親ではない、他の誰かとの絆があったから。
それが誰かは思い出せないが、そのことを考えると、胸の奥がチクリと痛んだ。
確かにある記憶。
思い出せない記憶。
思い出したくない記憶。
幼少の時を過ごしたというこの土地で起こるこれからのことを、秋次はまだ、何一つ知らない。
やがて夜も更け、秋次は自分の部屋のベッドに横になった。
(なんか、疲れたな)
この土地にやってきてからまだ3日目だというのに、秋次の周りでは色んなことが起こったので、無理もない。
それでも、こうやって一人で居ると、どうしても思い出してしまうことがある。
(あれは、本当に夢だったのかな…)
そっと唇に触れる。
思い出される甘い感触。
(夢じゃないなら、一体誰が……)
とりとめのない想いを抱きながら、秋次は寝息をたてはじめる。
そして、それは、そこに、居た。
秋次の寝顔覗き込むように、気配が動く。
「夢じゃ、ないよ」
その呟きとともに、気配がはじけ、やがて、消えた。
第二十一話「暁、目覚めの鼓動」へ