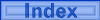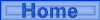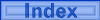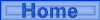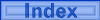AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
ハッピータウン!!
第二十一話 「暁、目覚めの鼓動」
目を開くとまだ慣れない天井。
時計の針はまだ6時を少し過ぎた程度。
いくら目覚ましより早く起きることが多いとはいえ、さすがにこれは早過ぎる。
けれど。
秋次は不思議と二度寝しようとは思わなかった。
「あれは、一体………」
夢を見ていた。
思いをはせればはせるほど忘れていく、そんな夢。
それでも秋次は考えずにはいられなかった。
(学校………月………二人………)
しかし、浮かんでくるのは輪郭のぼやけた単語ばかりで、なかなか像として結実されない。
(いや、三人…………つっぅっ!)
突然、左の瞼の奥に、突き刺さるような痛みを覚えた。
なんとか叫ぶのは堪えたものの、あまりの痛さに布団の上を転げまわる秋次。
その痛みで、一つ思い出したことがある。
この痛みを体験したのが、初めてではないということを。
「おはようございます」
「ん、おはよ……って、何か元気ないな?風邪か?」
心配そうな顔で椎奈が聞いてくる。
結局あの痛みは1分もしないうちに収まったものの、やはり不快感はしばらく残っているもので。
それが秋次の顔に現れていたのだろう。
「違うよ。ちょっと寝覚めが悪くて」
「大丈夫?」
「無理しちゃダメですよ」
美悠と永佳も秋次の顔を見て優しい声をかけてくる。
秋次にはそれがこそばゆくもあり、また、嬉しくもあった。
「大丈夫です。うん、大丈夫」
自分に言い聞かせるように、大丈夫を二度繰り返す。
『言葉には魔法がかかってるの』
いつか、誰かに聞いた言葉が浮かんで、手繰り寄せる糸をみつける間もなく霧散した。
「ならいいけど。うし、じゃあさっさと朝飯食うとしますか」
秋次の顔が普段通りに戻ったことを察したのか、椎奈もいつもの調子を取り戻す。
「そうだね。じゃあ、いただきます」
「いただきま〜す」
ちなみに今日の朝食は和風でごはんと味噌汁、それに納豆だった。
「ところでさ。今日って何の授業があるの?考えたら僕時間割とか何も知らないんだった」
「ああ、それなら大丈夫。今日は入学式だけだから。授業があるのは明日から」
秋次の疑問に椎奈が答える。
「入学式か………って、あれ?確か永佳さんの大学は昨日が入学式でしたよね?」
「大学に始業式という行事はありませんから」
微笑ながら永佳が答える。
「へー、そうなんですか」
「ま、それよりあたいはもう行くから。ごちそうさまでした」
「え、もう?」
秋次は時計を確認する。
昨日家を出た時間よりもまだ、20分程度早かった。
「ふふ、戦いはもう始まっているのだよ!」
やけに張り切っている椎奈。
「ねぇ、何があるの?」
「新人勧誘合戦。部活の」
美悠が妙に冷めた口調で呟く。
「ああ。まあ、確かにある意味体育会系のイベントではあるけど……」
中学から通してずっと帰宅部の秋次には、あまり縁のないイベントではある。
「というわけで、いざ、参る!」
妙な言葉を残して家を出る椎奈。
「ところでさ。椎奈のやってる部活って何?」
「行けばわかるよ」
あまりそのことについては触れてほしくないらしく、美悠の態度は非常に素っ気無い。
永佳に目を向けても、引きつった笑顔を返してくるだけであった。
「一体、何の部活やってるんだ?」
昨日より十分ほど遅く、秋次たち三人は家を出た。
「永佳お姉ちゃんはまだ遅くてもいいんじゃなかったの?」
基本的に、大学が始まるのは9時かららしい。
「たまには、皆で一緒に歩こうと思って。椎奈はいないけど」
「ところで、椎奈の部活…」
キッ。
何故か二人から睨まれた。
どうやら禁句らしい。
そうこうしている間に、桜華高校の門が見えてきた。
「本当、近いよなぁ」
「では秋次さん、また」
「気をつけてね」
一体何に気をつけるんだろうかと思った秋次だが、校門に近づくに連れてその言葉の意味を実感した。
「うわ……なんかギラギラしてるなぁ………」
そう、校門の向こう側には、新入生を待ち構える部活勧誘要員が獲物を狙う虎の如く目を光らせているのである。
その様子はまさに前門の虎。
幸い後門に狼はいないが、あそこを突破しなければ学校へたどり着けないので同じことだ。
ただ、秋次は二年生であるのでそれを理由にすれば勧誘を断るのは容易いと思われるが。
「でもなぁ」
一人、また一人と何も知らずに虎穴に入っていく新入生らしき人影の様子を見た後では、やはり躊躇われるというものである。
「おはよー、秋次君」
「ん、門の前で何やってんだ?」
秋次が門の手前で立ち往生していると、後ろからやってきた浩之とあかりに声をかけられた。
「あ、神岸さんに浩之。おはよう。いや、なんか入りづらくって」
「ああ、あれか。まあ年に一度のお祭みたいなもんだしな。そういやあかりんとこはあれに参戦しないでいいのか?」
「別にそこまでして部員が欲しいわけじゃないし。それに、何もしなくても好きな子は自分から来てくれるよ」
「ま、あかりんとこはそうだよな」
「神岸さん、何か部活に入ってるの?」
「うん。料理部」
ああ、と非常に納得する秋次。
「確かにあそこに見えるのって9割は体育系の部活みたいだね」
「体育会系は人数で勢力が決まるとこがあるからなぁ。みんな必死なんだろ」
「そういう浩之は部活は?やっぱ料理部?」
ちら、と隣のあかりを見る秋次。
「いんや、帰宅部。そういや秋次も前の学校では帰宅部だったっけか。こっちで何か始めてみようとか思うか?」
「いや、別に」
「じゃあ俺らと一緒にさっさと通り抜けようぜ。なんだかんだで俺には知った顔が多いから」
「うん、助かるよ」
こうして、秋次は浩之・あかりと一緒に校門をくぐった。
さっき浩之が自分で言ってたように、浩之を見かけると声をかけてくる生徒が結構いた。
まあ、勧誘要員の大半が自分たちと同じ二年生ということもあるだろうが。
「秋次!」
と、突然自分を呼ぶ声がしたので振り向くと。
「……………え?」
そこに居たのは、くの一だった。
くの一……女性の忍者。人目を忍ぶ職業だが、なぜかコスチュームの露出度が高い。
あまりの驚きに、思考に謎の説明文が混じる。
「っていうか、椎奈………?」
「椎奈ちゃん、おはよー」
「お前、まだ続けてたのか?それ」
そんな椎奈を見ても動じないあかりと浩之。
「いいだろ、好きでやってるんだし。それより秋次、うちの部活入らないか?」
「部活っていっても、部員お前一人だろうが」
「だから、正確には同好会だよ」
「はい、外野は黙ってる。で、どうなの?入るの?それとも入るの?」
そう言って入部届けを突きつけてくる椎奈。
(こ、こわい……)
どことなく声まで変わっている椎奈から受け取ったその紙には、大きく『くの一同好会』という名前が記されていた。
「くの一って、ねぇ、忍者とかじゃないの?」
「いや、くの一」
そこは譲れないらしい。
「じゃあどっちにしろ無理なんじゃ……」
「女装してでも。秋次ってちょっと女顔だし」
「うわ〜ん、椎奈がいじめる〜〜〜〜」
「あ、泣きダッシュ」
「椎奈ちゃん、ちょっとやりすぎなんじゃ」
「ところで浩之」
「んあ」
「あんたも入んない?」
全然懲りていない椎奈であった。
・・・・・
第二十二話 「入、世代の歪」
「あれ?」
謎のくの一、というか椎奈から咄嗟に逃げ出した秋次はいつのまにか知らない場所へ迷い込んでいた。
「二日連続で迷うなんて、なんだかなぁ」
とはいえ、この学校に来たのが今日で二回目、しかもろくに校内案内すらされていないとあっては致し方ないと思うが。
「さて」
耳を澄ますと、まだ校門の喧騒が届いてくる。
そこに向かえば校門にはたどり着くと思うが、再びあの側を通るのは気が滅入る。
それに、まだ謎のくの一が居るかもしれない。
幸い、近くに渡り廊下が見えるので、秋次はそこから室内へと入ることにした。
「って、あれ?」
その渡り廊下を道なりに歩いていると、急に同じ方向に進む生徒が増えてきた。
さすがに土足で廊下を歩くほど神経が太くない秋次は靴を右手に持っていたので、何事かとちらちらと見やる生徒が多い。
(参ったなぁ)
どうやったら靴が目立たなくなるだろうかと歩き方を変えたり持つ角度を変えたりしてみるが、余計目立ってしまう。
こんなことならくの一になってたほうがましだったかと思い、一瞬自分のくの一姿が頭をよぎったが、そのビジュアルは今の状
況が可愛いものだと思えるくらいに凄烈なものであった。
そんなショック療法的な方法で平常心を取り戻した秋次は、それから普通に歩いた。
そして人の波に流されるままたどり着いた場所はというと。
「入学……式?」
そう、そこは紛れもなく入学式の会場である体育館であった。
次々と体育館の中に吸い込まれていく新入生とおぼしき生徒達。
秋次は戻ろうとするが、波に逆らって移動するのは大変で、なかなか動き出すタイミングが掴めない。
やっとのことで動き出せたのは、まもなく入学式が始まる頃。
が、しかし。
「あら?あなたそこで何してるの?」
戻り始めた秋次の前に、先生と思しき女性が立ちはだかった。
「はは〜ん、さては遅れて来て自分のクラスが何処かわからないのね?」
ちらりと秋次の持つ靴に目をやる女性。
「あ、いや、これは」
「いいからいいから。え〜と、あの右から2番目が私のクラスだから。とりあえずあの最後尾に混じっちゃいなさい」
「へ?」
「ほらほら、早く早く」
「へ?へ?へ?」
こうして、妙に押しの強い女教師に押し切られて、秋次は新入生でもないのに入学式に参加することになってしまった。
「それにしても、秋次のやつ遅いな」
同時刻。
2年B組の教室。
「やっぱり迷ってるんじゃないかな?まだこの学校に慣れてないだろうし」
「なんなら探しに行くか?」
「う〜ん、ボクはそこまでしなくてもいいと思うよ」
なぜか今はまだ居ない秋次の席の周りに集まっている浩之・あかり・祐一・あゆの四人。
ちなみに教室にはいつもの半分ほどの生徒しかいない。
残りの半分は、入学式の後行われる部活動紹介に向かったためだ。
「まさかあいつ、本当にくの一同好会に入って部活動紹介とかしてんじゃねーよな…………」
「やめろ浩之。今一瞬意識がブラックアウトしかけた」
「む、すまん」
「それよりあかりちゃんは部活動紹介行かなくてよかったの?文化部もやるんだよね、確か」
「うん、私たちは部長が簡単に紹介するだけだから。体育館で料理するわけにはいかないしね」
「ま、そりゃそうだ」
と、そんな他愛ない話を続けていると、ちらほらと教室に戻ってくる生徒が現れはじめた。
「よ、雅史。お疲れ」
「うん」
浩之が戻ってきた雅史に声をかける。
ちなみに雅史はサッカー部員だ。
「そうそう雅史ちゃん、秋次くん見なかった?」
あかりが雅史に聞く。
すると、雅史は何故か複雑な表情で、
「う〜ん、見たような見なかったような………」
「ん?どうした佐藤、言い澱むなんてお前らしくないな」
そんな雅史の様子に疑問を抱いた祐一が言葉をはさむ。
「うん、見かけたような気はするんだ。部活動紹介の時に」
「は?」
「へ?」
「え?」
「うぐぅ?」
「あゆ、そこうぐぅの使い方間違えてない?」
「あ、椎奈ちゃんお帰り」
「つーか同好会は部活動紹介の時間なんてないだろ?なんで雅史より遅く戻ってくるんだよ」
「くの一のヒミツ」
「わけわかんねー」
「それはそうと、私も体育館で秋次らしき人物を見かけたわ」
「私も見たよー」
「お、名雪も戻ってきたか」
ちなみに名雪は陸上部である。
「なんかねー、新入生の一番後ろに秋次君いたよ?」
「やっぱり、目の錯覚じゃなかったのか。………でも、何で?」
「俺に聞くな」
「えー、新入生気分を味わってみたかった、とか」
「いや、ある意味秋次も新入生だろ。昨日転校してきたばっかなんだし」
「それもそうだね」
「ま、本人に聞けば早いだろ。丁度良く戻ってきたことだし」
教室の扉に目をやると、そこには普段の三割増しで疲れた顔をしている秋次が居た。
「おーい、秋次。ご入学おめでとー」
「おめでとー」
椎奈の音頭に続いて皆が一斉に叫ぶ。
「あ、ドア閉めた」
「あの足音は、泣きダッシュだね」
「ってか、なんかこのパターンが多いな最近……」
とりあえず。
今回は秋次は教室に向かってきていた沙夜にすぐに発見・捕獲されたので道に迷うまでには至らなかった。
・・・・・
第二十三話 「浸、透過する思考」
「と、いうわけで。こちらが新入生の遠藤秋次君よ」
沙夜のその紹介に、ダッシュで教室から逃げ出そうとする秋次。
しかし、沙夜が素早く引き戻す。
「離してください!僕はアンドロメダ星雲に帰ります!」
「アンドロメダ星雲かどうかはわからないけど、離すとまた迷子になるだろうから離しません」
「………なあ、ここって教室だよな?」
「多分、一応、そのはず……」
教壇の前で繰り広げられる寸劇を見ながら、ひそひそと話す椎奈とあゆ。
「とまあ、冗談はこれくらいにして皆席に着いて」
しばらく息を荒げていた秋次が落ち着いたのを見て、通常モードに戻る沙夜。
沙夜のその言葉で、教室は一応の落ち着きを取り戻した。
「じゃあHRを始めるわね」
その後は、沙夜が連絡事項を告げるだけで淡々と時間が過ぎていった。
「今日はこれでお終い。明日から平常授業になるから、いつまでも休み気分じゃだめよ」
そして、委員長の挨拶でHRが終わる。
「さて」
「さて」
「さて」
HRが終わった瞬間に、秋次に三方向から同時に声がかかる。
椎奈・浩之・志保が秋次を囲んでいた。
「さっきの話詳しく聞かせてもらいましょうか」
「つーか、志保。なんでお前が居るんだ?クラス違うだろーが」
「ほほほほ、それはもちろん企業秘密よ」
わざとらしくお嬢様ポーズをとる志保。
「まあいいけどな。で、秋次、新入生になった感想はどうよ?」
「ってかなんで入学式に?しかも靴持って」
「……………帰る」
こういう質問を受けるだろうことは予想していた秋次ではあったが、どうにも答える気が起きなかった。
実際のところ、なんで入学式に参加することになったのか、自分でもよくわかっていないのだ。
強いて言うならば、流された、だろうか。
秋次は、静かに席を立つと、引き止める椎奈たちの声も耳に入らない様子で教室を後にした。
(それにしても)
思い出したくはないが、どうしても浮かんでしまう入学式の様子。
場違いな闖入者に向けられる疑惑の視線。
異物の混入を拒絶する視線。
それは単に、秋次の被害妄想にすぎないかもしれないが、秋次はそういう視線を感じていた。
ただ、一つだけ異質の視線を感じた。
興味・慈愛・畏敬・崇拝・感謝・激励・期待…………
どれも、違う感じがする。
でも、そのどれでもあるような気もする。
(なんだったのかなぁ)
そんなことを思っているうちに、秋次は昇降口に着いていた。
「あれ?」
自分の下駄箱を覗くと、そこにあるはずの靴がなかった。
なぜなら。
「…………ずっと持ったままだったのか………」
そう、秋次の右手には、しっかりと靴が握られていたのである。
考えてみれば。
秋次は今始めて自分ひとりで校門をくぐったことになる。
振り返って校舎を見渡す。
校庭には八分咲きの桜。
『桜華高校』という名に対しては、ちょっと規模が小さい感じが否めないのが難点だが。
それでも、充分見応えがある。
その桜並木を通り、下校する生徒たち。
この学校の最大の売りであるらしい女子の制服の多彩さは、ただ眺めているだけでも心が晴れやかになるので不思議だ。
広いグランド。
新しい体育館。
「何やってんだ?」
そして、新しい友。
「学校をね、見てたんだよ、祐一」
「ふーん。そんなの見て面白いかねぇ」
「そういえば、祐一も転校してきたんだよね」
「ああ」
「こうやって感傷に浸ったことってない?」
「ない」
即答だった。
「どうでもいいが、あんまりそうやってるとアブナイ人だと思われるぞ」
「え?」
「つまり。とっとと帰ろうぜ」
そう言って歩き出す祐一。
「あ、うん」
慌てて後を追う秋次。
「あれ?でも祐一の家ってこっちじゃないんじゃ……」
「商店街に寄るんだよ。ほれ、とっとと行くぞ」
どうやら、秋次に拒否権はないらしい。
こうして、祐一と秋次は商店街へと向かって行ったのだった。
【to be continued……】