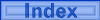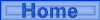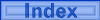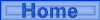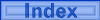AIで普通の動画を3D動画に変換する
ハッピータウン!!
第一話 「春、目覚める町」
駅の構内を一歩抜け出ると、目の前に鮮やかな桜の並木が映し出された。
しかし、旅装にしては少な目の荷物を抱えた彼がこの街に着いて発した第一声は、
「ふぅ……」
というため息だった。
(あれは、なんだったんだろう……)
晴れ渡った空を仰ぎ、彼、遠藤秋次はさっきの出来事を頭の中で反芻していた。
秋次はこの町にやってくる電車の中で一人の少女と出会った。
少女は、秋次が寝ている間に、何時の間にか隣に座っていた。
秋次が目を開いた時、少女の顔が目の前にあった。
そして、覚醒しきっていない秋次と、唇を重ねた。
一瞬の出来事だった。
それでも秋次は何事もなかったかのように眠りについた。
次に目を覚ました時、隣に少女の姿はなかった。
今度は完全に目を覚ました秋次は事の重大さにようやく気付く。
(もしかして、キスされたの?!)
慌てて少女の姿を捜すが、もはやどこにも見当たらない。
それに、秋次はその少女の姿をほとんど覚えていなかった。
そう、それは夢のような出来事だったのだ。
(…………………やっぱり、夢だったのかな)
そう思う秋次ではあったが、それを否定するように、唇には甘い感触が今でも残っている。
そんな夢心地を味わいつつも、秋次はこの町での暮らしへの第一歩を踏み出していたのだった。
芙蓉町。
それが秋次がこれから暮らすことになる町の名前だ。
そして、秋次が幼少時代を過ごした土地でもあったが、秋次は全く覚えていない。
秋次がこの町に来ることになった理由は、何故か彼の両親が海外に移住することになり、今まで住んでいた家を手放すこと
になったからだ。
しかも、今両親が住んでいる国の名前を、秋次は聞いたこともなく、どの辺に位置するのかも全くわからない。
秋次がそんな国には行きたくないというと、両親も最初から彼を連れて行くつもりはなかったらしく、それじゃあ親戚のと
こに行け、もう連絡はしてあるから、と列車のチケットと地図を渡されたのだった。
よく考えてみると横暴な話ではある。
しかし、秋次に拒否権はなかった。
彼が暮らせる場所は、もう、そこ以外になかったのだから……
地図を頼りに目的の場所を探す。
地図はかなり詳細に書かれており、すぐに見つかると思えたが、なかなかどうして、土地勘がないと無闇やたらと歩き回っ
てしまう。
そして、やっとのことで見つけたその家は、いかにも普通の一軒家だった。
「え〜と、遠藤……あった、あった。ここ、かな?」
「うん、そうだよ」
「よかった………って、え?!」
急に背後からした声に驚いて振り返ると、そこには手にたい焼きを持ち、背中に羽の生えたバッグをしょった背の低い女の
子が立っていた。
「君、ここの家の人?」
「ううん、違うよ」
笑顔でたい焼きを頬張りながら、少女が答える。
「じゃあ……」
しかし、秋次の次の質問は少女の言葉によって遮られた。
「ボクはあゆ。月宮あゆっていうんだ」
・・・・・
第二話 「扉、暮らすべき場所」
「鮎?って魚の?」
「うぐぅ、ボクは魚じゃないよ」
そう言ってあゆは拗ねた顔をした。
「え、いや、そういうつもりじゃ……」
あゆの意外な反応に、秋次は少し戸惑ってしまった。
しかし、あゆはそんな秋次のことなど気にした様子もなく、すぐに笑顔を秋次に向けた。
「君は?」
「え?」
「だから、君の名前だよ」
「あ、ああ。僕は遠藤秋次っていうんだ」
「遠藤?」
そう言ってあゆは秋次と遠藤家を交互に見ていった。
「どうしたの?」
「ん、秋次君、椎奈ちゃんと何か関係あるの?」
「椎奈ちゃん?」
「あ、あゆ発見!!」
と、突然家の扉が開いたかと思うと、中から勢いよく女の子が飛び出してきた。
春とはいえ今日はそんなに暖かくはないのに、その少女はTシャツにハーフパンツというラフな格好をしていた。
どことなく猫的な印象を受ける、ショートカットのよく似合う女の子である。
「椎奈ちゃん、こんにちは」
「『こんにちは』じゃない!いつまで人を待たせる気だ!」
「うぐぅ、ごめん」
「ということで、このたい焼きはいただくことにする」
言うが早いか、椎奈はあゆが大事そうに胸に抱えていた袋を素早くひったくった。
「ああっ、それ最後の一個なのに……」
「遅れるあゆが悪い」
「うぐぅ」
「ん?ところであゆ、今日は彼氏連れなのか?」
誇らしげに戦利品を頬張っていた椎奈は、ようやく秋次の存在に気付いたようだ。
「え?あ、いや、僕は……」
「彼氏じゃないよ。全然知らない人」
なにもそこまで強く否定しなくても、と思う秋次であったが、その全然知らない人にいきなり声をかけてきたのは、何を
隠そうあゆである。
「で、あんた誰?」
「えと……」
「秋次君だよ」
「なんで、あゆが名前知ってるんだ?さっき知らない人だって言ってたじゃんか」
「それはさっきまでの話だよ。今じゃすっかりお友達なんだ」
「そうなの?」
「そうなの」
「そうかい、あゆのダチだったらあたいのダチだね。あたいは遠藤椎奈。椎奈って呼んでくれ」
「ボクは月宮あゆ」
「あゆは黙ってな」
「うぐぅ」
「僕は遠藤秋次」
「ん?遠藤?」
そういって椎奈はふと視線を空に向け何やら考える。
「………あ〜〜!!あんたもしかして、今日から家に住むっていう親父の兄貴の息子って人か!」
「いや、もしかしなくてもそうなんだけど。それに、従兄弟っていったほうが早いんじゃ………」
「そ、それは、そう、オトナのジジョーってやつだよ。ま、それはおいといて、立ち話もなんだから早いとこ家に入ろうぜ」
そう言って椎奈はさっさと家の中に入っていってしまった。
急な展開についていけず、半ば呆然として立ち尽くしている秋次の横をあゆが通り過ぎようとする。
「どうしたの、秋次君」
「あ、月宮さん……」
「あゆでいいよ」
「わかった、あゆちゃん」
「うん。早く入んないと、椎奈ちゃんまた怒っちゃうよ?」
「そうだね」
こうして、秋次はあゆと一緒に遠藤家の門をくぐるのであった。
・・・・・
第三話 「縁、認める者たち」
「おじゃましま〜す」
「お邪魔します」
「あら、あゆちゃんいらっしゃい」
そういってあゆたちを迎えたのは椎奈ではなく、ほっそりとして背が高く、長い黒髪がとてもよく似合う和風の美人だった。
「あ、永佳さん。こんにちは」
「こんにちは。椎奈ならさっきリビングに行ってたわよ。……あら?」
あゆに永佳と呼ばれたその女性は、ようやく秋次に気づいたようだ。
「もしかして、あゆちゃんの彼氏?」
「ううん、違うよ」
「そうだぜ、姉貴。そいつは今日からあたいらと一緒に住む従兄弟の秋次さ」
いつの間にか顔を出していた椎奈が秋次のことを簡単に説明する。
「まあ、そうだったの。ごめんなさいね。私は遠藤永佳。一応、椎奈の姉です」
「なんだよ、一応ってのは!」
「まあまあ」
永佳にくってかかる椎奈をあゆがなだめる。
それは、本当に何気ない光景であったが、その自然さが不思議な安心感を秋次に与えた。
「えーと、僕は遠藤秋次です。これからよろしくお願いします」
深々と頭を下げる秋次に、椎奈が苦笑しながら話かけてきた。
「おいおい、これから一緒に暮らすんだぜ?他人行儀はやめにしないか」
「そうですよ。ここは、もう、秋次さんの家でもあるんですから」
「そうそう、遠慮はいらないよ」
「あゆは関係ねーだろうが!」
「うぐぅ」
あゆたちのやりとりを見ていると、秋次の顔には自然と笑顔が浮かんでいた。
「じゃあ、改めて。これからよろしくお願いします」
その言葉は、さきほどのように他人行儀な挨拶ではなく、いたって自然に口をついた言葉だった。
「お、いいねえ。まあ、なんだ。これからヨロシクな!」
ビシッ!と親指を立てて椎奈が言う。
「わからないことがあったら、なんでも聞いてくださいね」
穏やかな微笑みを浮かべて永佳が言う。
「とりあえず、今日の晩御飯はカレーだよ」
「なんであゆが知ってるんだ?!」
「んとね、美悠ちゃんから聞いたんだ」
「美悠?」
初めて聞く名前に、秋次は思わず呟いていた。
「ああ、美悠っていうのはあたいたちの妹のことだよ。そういや、姿が見えねーな。確か家には居たと思うんだけどなあ……」
「あら?さっきまでリビングに居たはずだけど?」
「いや、あたいは会わなかったぞ」
「あの、美悠ちゃんならここだよ」
そう言ってあゆは自分の背後に回りこむようにターンを決めた。
するとそこには、
「!!」
あゆより多少背の高い、ポニーテールの少女が中腰のまま固まっていた。
が、自分が場に現れたことを悟ると、今度は素早く椎奈の後ろに隠れてしまった。
「お、秋次、よかったな。美悠はお前のことが気にいったみたいだぞ」
「え?!」
とてもそうは思えない。
「珍しいわね。美悠が男の人を気にいるなんて……今日はお赤飯かしら?」
「でも、カレーにお赤飯はあわないと思うよ」
「それもそうね」
などと盛り上がる女性陣であったが、秋次には何が何やらさっぱりである。
ふと、椎奈のほうを見てみると、美悠が顔を少しだけ覗かせていた。
「……よ、ヨロシク……」
美悠は、それだけ言うとまた椎奈の後ろに隠れてしまった。
(い、一体なんなんだ?!)
そこはかとない不安を感じながらも、三姉妹からはどうやら遠藤家の一員として迎え入れられた秋次であった。
・・・・・
第四話 「階、垣間見る過去」
「あ、そういえば叔父さんたちは?」
美悠以外とはすっかり打ち解け、リビングでトランプやUNOに興じていた秋次が、思い出したようにそういった。
ちなみに、美悠はその様子を永佳の後ろからちらちら覗いていたようだ。
「ああ、親父なら部屋にこもってると思うぜ。お袋は出張かなんかで当分帰って来ないらしいけどな。親父、呼んで
こようか?」
「いいよ。僕が行くから」
「……私が行く……」
美悠が久しぶりに口を開いたかと思うと、疾風のような速さでリビングから消えていった。
「ちゅう事だから、ここで待ってな」
「うん」
「あら?どうしたの、あゆちゃん。さっきから元気ないわね」
「うぐぅ。いっぺんも勝てなかったよ……」
「まあ、勝負は時の運だべ」
「うぐぅ。椎奈ちゃん強すぎるよ……」
もはや半ベソ状態のあゆであった。
「おお、秋次君。久しぶりだね」
そこへ、この家の主・遠藤稔が現れた。
長身で少し痩せているような感じを受け、柔らかい物腰と眼鏡が知的な雰囲気をかもし出している。
体育会系の秋次の父親とは正反対と言ってもいいだろう。
「といっても、この前あったのは12年も前だ。覚えてるかい?」
「……すみません」
秋次にはこの叔父に会った記憶がない。
「いや、いいんだよ。……それに、無理に思い出すようなことじゃない……」
稔の言葉はだんだんと小さくなっていき、最後の方はほとんど独り言に近くなっていた。
秋次たちにその言葉は届かなかったものの、稔の表情に感化され誰も言葉を発せなくなっていた。
少しの間、沈黙がリビングを支配する。
その沈黙を破ったのは、稔の後ろに隠れていた美悠だった。
「……パパ、お腹すいた……」
「ああ、もうそんな時間かい。それじゃあみんな、そろそろ夕飯にしよう」
「はぁ〜い」
「あゆちゃんも食べていくかい?」
「う〜んと、ボクはもう帰ることにします」
「なんだよあゆ、食ってきゃいいのに」
「そういうわけにもいかないよ。それじゃ、おじさん、椎奈ちゃん、永佳さん、美悠ちゃん、秋次くん、またね」
「またいらっしゃい」
「おう、気をつけてな」
「道草しちゃだめよ」
「…バイバイ」
「じゃあね」
こうしてあゆは、パタパタと手を勢いよく振りながら遠藤家を後にした。
「へぇ〜、このカレーって美悠ちゃんが作ったんだ」
「ええ、今日は美悠の担当でしたから」
食卓を囲んで家族団欒の会話が続いている。
「うちは恵都がいないことが多いから家事は分担してやってるんだよ」
「恵都?」
「……ママの名前……」
ちなみに、美悠はずっとうつむいたままカレーを食べている。
「そうなんですか。じゃあ、叔父さんも料理したりするんですか?」
「まあ、する時もあるんだけどね」
そう言って稔は苦笑する。
「親父の料理は確かにうまいんだけどさ。時間がかかりすぎるんだよな」
「ええ。晩御飯の準備を午前中からしてますもんね」
「はぁ……」
「それより秋次。このカレーの感想を美悠に聞かせてやってくれねーか」
「ん?おいしいよ?」
「それだけか?」
「うん。だっておいしいんだもん」
「そうか。よかったな美悠、おいしいってよ……って、ありゃ?美悠は?」
椎奈が見たときには既に美悠はその席にはいなかった。
「美悠なら、ほら」
永佳がくいっと顎を動かす。
「……おかわり、どうぞ……」
「あ、ありがとう」
するとそこでは、いつのまにか秋次の隣に移動していた美悠が、秋次におかわりをすすめていた。
「美悠、なかなかやるな」
稔はその様子を温かい目で見守っていた。
秋次はすっかり遠藤家の食卓に違和感なく溶け込んでいたのだった。
・・・・・
第五話 「夜、理由なき誘い」
「ごちそうさまでした」
美悠が食べ終わったところで皆そろって食後の挨拶をする。
どうやら、全員食べ終わるのを待つのが遠藤家の習慣らしい。
「じゃ、とっとと洗っちまおうぜ」
「そうですね」
「あ、僕も手伝います」
「うん」
食事の後片付けは皆でやるようだ。
そのため、10分足らずで綺麗に片付いた。
「じゃ、私はまた部屋にいるから。何かあったら呼びにおいで。あ、それと秋次君の部屋は二階の一番奥の部屋だから」
ちなみに、稔・永佳・椎奈・美悠の部屋も二階にある。
外側から見ただけでは分からなかったが、どうやらかなり奥行きのある広い家のようだ。
「はい、わかりました」
「今日からここが秋次君の家だからね。何も遠慮することはないよ」
そう言って稔は自分の部屋へと戻っていった。
「そういや、秋次の荷物ってかなり少なかったけど、本当にあれだけか?」
「そうだよ」
「荷物って……あれですか?」
永佳がちらりと目をやった先には旅行用バッグにしては少し小さめのバッグと普通のスポーツバッグがこじんまりと置いて
あった。
「そうです。必要最低限のものしか持ってきてませんから」
「………他の物は?」
「友達にあげたりとか。でも、僕の部屋にあったものはほとんどあの中に入ってるよ」
「マジ?!あんたって物を持たない主義なのか?」
「う〜ん、どうだろ。普通だと思うけどな」
「………で、一体これはどっからでてきたんだよ!!」
秋次の部屋に遊びにきた椎奈と美悠が目にしたのは、部屋いっぱいに広がった秋次の私物の数々である。
「どっからって、バッグからだけど……」
「嘘つけ!このコンポなんかどう見てもバッグに入んねーぞ」
「……目覚まし、可愛い……」
ぼうっと辺りを見回すだけの椎奈に対して、美悠はもの珍しそうに部屋の中を動き回り、イワトビペンギンの姿をした目覚し
時計を見つけてじっと見つめていた。
「気にいった?欲しかったらあげるよ」
「いいのか?」
「うん。僕は目覚ましなくても起きれるから。それに時計はもう一つあるしね」
そういう秋次の視線の先には、四角で青い普通の目覚ましがあった。
「……あ、ありがとう」
美悠がそのイワトビペンギンをぎゅっと抱いて秋次にお礼をいった。
とりあえず、もう隠れなくても喋れるようにはなったようだ。
「ところで秋次、明日暇か?」
「用事があるように見える?」
「まあそれもそうか。じゃあ、明日あたいと美悠が街を案内してやるよ。春休みも明日で終わりだしな。本当は姉貴も来たが
ってたけど、なんか用があるみたいなんだ。ま、覚悟しとけよ」
「覚悟?何の?」
「そいつは明日のお楽しみさ。それじゃ、秋次、おやすみ!」
「……おやすみなさい」
こうして、一抹の不安を残しつつ、遠藤家の夜は更けてゆく。
・・・・・
第六話 「外、澄み渡る空」
「おはようございます」
午前8時30分。
休日としては早めの時間に秋次は目を覚ました。
とはいっても、それは世間一般での話であって、いつもは7時30分頃に目を覚ます秋次にとっては遅い起床といえる。
とりあえず、誰もいないだろうと思いつつもリビングまで降りると、意外なことに永佳が朝食を食べていた。
「あら、おはようございます。もうお目覚めですか?」
「ええ、習慣なもので。永佳さんは?昨日椎奈が用があるとか言ってましたけど……あ、デートですか?」
「いいえ、残念ながら。大学の入学式なんですよ」
「へえ。大学ですか。大変そうですね」
「まあ、行ってみないことにはなんともいえませんけどね」
「それもそうですね。あ、それより時間大丈夫ですか?」
「えーと、え?もうこんな時間?!急がなきゃ……じゃあ、秋次さん、行ってきます」
「お気をつけて」
こうして慌ただしく出て行った永佳を見送った秋次は、昨日の残りのカレーを温めて食べようかとも思ったが、せっかく
だから誰かが降りてくるのを待つことにした。
しばらくリビングでテレビを見ていると、とてとてと階段を降りてくる音がした。
「美悠ちゃん、おはよう」
降りてきたのは美悠だった。
「……お、おはようございます」
「お、はぇ〜な、秋次」
そのすぐ後ろには椎奈の姿も見える。
「もう飯は食ったのか?」
「ううん。みんなと食べようと思って」
「そうか。なら、とっとと食っちまおうぜ」
「叔父さんは?」
「……パパは朝食べないの」
「そういうこと。んじゃ、ちゃっちゃとカレー食って街に行こうぜ」
「遅いぞ、美悠!」
「ごめんなさい、てへっ」
そう言って美悠は少しはにかんだ顔を椎奈に向けた。
朝食を食べ終わった三人は、一旦準備をするために部屋に戻り、それからリビングに集まることにした。
とは言っても、秋次に着替えや準備するものなどなく、空になったスポーツバッグを担ぐだけでリビングに向かった。
椎奈は一応着替えたようだが、Tシャツの色が緑から赤に変わったくらいで他に変化は見られない。椎奈は何故か秋次より
先にリビングにいた。
そして先ほど、美悠がリビングに現れたのである。
「まあまあ。それより、今日はどこに連れていってくれるの?」
「ふふふ。それはついてからのお楽しみってことで」
「……ゲーセン?」
「ゲームセンターですね」
「そう!ここはゲーセン!!」
「それにしても、なんでまた」
正直、意外だった。
椎奈は見た目、性格ともに生粋のスポーツマンだ。実際、運動神経もかなりのものらしい。
そんな椎奈とゲーセンの接点を、秋次は見つけられずにいた。
「お、椎奈。今日も来たのか」
しばらくぼーっと突っ立っていると、ゲーセンの店員らしい男が椎奈に声をかけてきた。
「今日は美悠ちゃんも一緒なんだな。おっす、美悠ちゃん」
「浩之さん!!」
突然、美悠はものすごい勢いでその店員に抱きついていった。
「ぐっ、今日もナイスタックルだぜ、美悠ちゃん」
「えへ」
その様子をただ見守っていた秋次に、椎奈が声をかける。
「美悠が一番なついてるのは、今んとこ浩之だからな。あんたも覚悟しといたほうがいいかもよ」
そういって椎奈は悪戯な笑みを浮かべた。
「……体、鍛えよう……」
本気でそう思う秋次であった。
「ところで、椎奈。お前、彼氏できたんだな。そこの彼氏君、椎奈のことをよろしく頼むぜ」
「あ、いえ、こちらこそ」
思わずそう答える秋次であった。
ちなみに、美悠はまだ店員にくっついている。
「な、なに言ってるんだよ!こいつはうちの従兄弟で遠藤秋次っていうんだ。別に彼氏とかそんなんじゃ……」
「わーってるって。俺は藤田浩之。一応そいつのクラスメイトな」
「あっさり否定されるとなんかムカツク」
「椎奈のクラスメイトってことは同じ学年だね。僕は遠藤秋次。秋次って呼んでいいよ」
「そうか。んじゃ、おれのことも浩之でいいぜ」
「うん。よろしくね、浩之」
「ああ。こっちこそな、秋次」
何故かがっちりと握手を交わす秋次と浩之であった。
・・・・・
第七話 「音、躍動する肢体」
「う〜ん、いいわね〜。これぞ男の友情、って感じ?」
固く握手を交わす秋次と浩之に、女性の店員が近づいてきて話し掛けてきた。
「あ、玲子さん。すんません、すぐ戻ります」
浩之に玲子と呼ばれたその店員は、微笑んで軽く手を振った。
「いいのよ、別に。今日は店長もいないんだし、しっかり友情を温めてねん」
「はあ……」
「と・こ・ろ・で」
と、突然玲子の声音が変わる。
その変化を敏感に察知した浩之は、
「玲子さん、やっぱり仕事しなくちゃまずいっすよ。おれ、あっちの掃除してきます」
そう言って素早くこの場を立ち去ってしまった。
「もう、浩之クンてばいつも逃げるんだから。あたしも仕事に戻ろ〜っと。椎奈ちゃんたちはゆっくりしてってね」
玲子は軽くウインクを残して去っていった。
「……一体何だったの?」
「あたいも、あの人のことはよくわからん」
「あ、そういや美悠ちゃんは?」
いつの間にか、美悠は秋次の周りから姿を消していた。
「美悠なら、ほら、あそこで浩之の邪魔してる」
そう言って椎奈が指差す先を見ると、なるほど、美悠が浩之の後をついて回っていた。
本人は手伝っているつもりだろうが、傍から見れば邪魔以外のなにものでもない。
それでも邪険にしていないのは、浩之の優しさか、周りに見えないだけで実は本当に役に立っているのか。
もっとも、後者の確率は恐ろしく低そうだが……
「さて、美悠のお守りは浩之に任せて、あたいたちは遊ぼうぜ」
「お守りって……」
「細かいことは気にしない気にしない」
そう言ってさっさと歩き出す椎奈であった。
「さてと……」
その場所に着くと、椎奈は体を回したり屈伸をしたりして体をほぐし始めた。
ここは、体感ゲームコーナー。
その中でも、音にあわせて色々なアクションを要求される、いわゆる「音ゲー」が集められた場所に秋次たちはいた。
で、椎奈がやろうとしているのは、画面に流れる矢印にあわせて足元のパネルを踏む、音ゲーの中でも最もポピュラーなものの
最新版である。
秋次も何度かやったことがあるが、ある程度難易度が高くなると急にバタバタとしてすぐにゲームオーバーになってしまった。
「今日までこれ、1プレイ100円なんだ」
確かに、そのゲームの上には「期間限定サービス台1PLAY100円」と大きく張り出してあった。
そのためか、まだ開店してそれほど時間は経っていないというのに、すでに10人ほどが並んでいた。
「どした?秋次はやんないのか?」
「うん。僕はちょっと見てるよ」
秋次はさっきからプレイ中の少女の動きに目を奪われていた。
その少女は「ほっ」とか「はっ」とか声をあげたり、ギャラリーに向かって手を振ったりと無駄な動きが多かったが、それでも
ライフゲージは増える一方だった。
むろんノーミスである。
その少女がプレイを終えると、自然と歓声が沸きあがった。
少女はスコアのトップに「SHC」と名を刻むと、ギャラリーに向かって笑顔を振り撒いた。
「……あの娘だったんだ……」
呟く椎奈の声に振り向くと、何故か椎奈は闘志をたぎらせていた。
そして、
「長岡さん!」
急に叫んだ椎奈の声で辺りは一瞬静かになる。
「長岡志保さんよね?桜華高校の」
「そうだけど。あなたは、確か、遠藤さん?」
「そう。あたいは遠藤椎奈」
「……シーナ?まさか!あなたが『C7』なの?!」
「その通り。驚いたよ、まさか『SHC』がうちの高校の同級生だったなんてね」
「そりゃこっちの台詞よ。私のスコアが破られてるだけでもショックだったのに、まさかそれが同い年の女の子だったなんて」
椎奈と志保の視線が交錯し、見えない火花があたりを焦がす。
まさに、一触即発とはこのことだろう。
そんなことを考えながら、自分はすっかり蚊帳の外の秋次であった。
・・・・・
第八話 「舞、魅了される群衆」
「じゃあ、早速始めましょうか」
「駄目ね」
「へ?!何で?」
非常に間の抜けた声を志保があげる。
「何でって、ちゃんと順番は守んないとね」
そう言って椎奈は自分の隣をクイッと指差した。
「あ、そういうことね」
納得した志保はひょいひょいと椎奈の横に並んだ。
「よろしく、長岡さん」
「う〜ん、その『長岡さん』って呼ばれるのなんか背中が痒いのよね〜。志保でいいわよ」
「そう。じゃあ、あたいのことも椎奈で構わないよ、志保」
「うんうん、そうこなくっちゃ」
そんな事を話していると、程なく椎奈たちの番がやってきた。
秋次が周りを見回すと、どこから噂を聞きつけたのかギャラリーの数が3倍くらいに膨れ上がっていた。
「おいおい、なんだよこの人だかりは」
後ろから、浩之の声が聞こえた。
美悠はしっかりと浩之の服を握って側に居た。
「うん、なんだか椎奈と誰かが対戦するみたいなんだ」
「へー、命知らずなやつがいたもんだ……って、あれ志保じゃねーか?」
「え?知り合いなの?」
「ああ、一応な。しかし、これでこのギャラリーの数にも納得がいくぜ」
そう言って浩之は一人でうんうんうなずいている。
と、突然辺りが一瞬の静寂を迎える。
椎奈たちの方を見てみると、今まさにコインを投入し終えたところだった。
「いよいよだな……」
浩之の言葉に、秋次は無意識につばを飲み込んでいた。
浩之の服を握る美悠の手にも、力が入っているようだ。
そして、二人の少女の舞いが、今、始まる。
二人が選んだのは「ノンストップ」方式。
これは、通常のステージクリア型とは違い、ステージ間にインターバルはない。
休憩する間がないのはもちろんのこと、いきなり曲のテンポが変わるので非常に難度が高い。
しかし、椎奈と志保はそんなことなどお構いなしとばかりに華麗なステップを披露し続けている。
志保は相変わらずギャラリーに愛想を振り撒いて無駄な動きが多そうに見えるが、着実にコンボを重ねている。
一方、椎奈の方はギャラリーなどは気にせずに、ひたすら自分のペースでステップを踏みつづける。
しかし、そのスマートでスピーディーな足さばきは、人の目を引きつけづにおけない魅力を放っていた。
要するに、二人とも達人レベルなのだ。
もっとも、大会に出た事はないので、全国でのレベルはわからないが、このゲーセンに来る客のほとんどが、どちらも全国で
優勝できると信じて疑わない。
そう、今回のバトルは、事実上の日本一を決めるバトルといっても過言ではないのだ。
ギャラリーも、椎奈や志保のプレイを一度は目にした者たちが多いので、目は確かだ。
そして、プレイヤーが女の子ということもあり、応援にも自然と熱が入っていった。
「うぉ〜、ビューティホー志保ちゃーん!!」
「椎奈ちゃ〜ん!おれも踏んでくれ〜〜!!」
……あまり気持ちのいいものとは言えない歓声がフロア中に響いている。
秋次は、今までに体験したことの無い感覚に、頭がくらくらしていた。
「お!」
浩之の声に正気を取り戻した秋次が目にしたのは、パネルを踏み違えた椎奈の姿だった。
「勝負あったな」
浩之の言葉通り、バトルは志保の勝利で幕を閉じた。
一度タイミングを外した椎奈であったが、すぐに持ち返したのはさすがだった。
普通はあそこで間違えると修正は不可能に近い。
それでも、相手が志保では一度のミスでも致命傷だった。
その志保はというと、何故か志保を応援していたギャラリーから胴上げされていた。
「椎奈……」
いつの間にかさっきの2倍ほどに膨れあがったギャラリーをかきわけて、秋次は椎奈のもとに近づいていった。
「あ、秋次。負けちまったよ」
意外とさっぱりした顔で椎奈が応えてきた。
「さ、ちょうど腹も減ったし、飯でも食いに行こうぜ」
そう言って、さっさとその場を立ち去ろうとする。
「あ、ちょ、ちょっと」
慌てて後を追いかける秋次。
「さ、美悠ちゃん、行っといで」
「うん。浩之さん、バイバイ」
ぶんぶんと手を振りながら、椎奈のところに向かう美悠。
「椎奈!」
出口へ向かう椎名を呼び止める志保。
「また、やりましょうね」
「ああ、次は負けないからね!」
そして、笑顔で返す椎奈だった。
・・・・・
第九話 「昼、満たせ空腹」
ゲームセンターを後にした秋次たちは、昼ご飯を食べるために商店街をうろついていた。
「ねえ、どこに行くの?」
「『HONEY BEE』」
「ハニービー?なんか甘そうな名前だね」
「……別に甘くないよ。喫茶店の名前なの」
「そっか。いきなりお店の名前言われてもどんなとこかわかんないよ」
「結構有名なんだけどな」
「そりゃ、この辺じゃ有名かも知れないけど、僕は昨日この町に来たばかりなんだよ?」
「あ、そうか。悪い悪い。なんか、秋次はずっとこの辺に住んでるみたいに思えたんだ」
「それは、喜んでもいいのかな?」
「いいんじゃねえか?それだけ、秋次がこの町に馴染んでるってことだろうしな。お、あったあった」
見上げると、そこには確かに「HONEY BEE」と書かれた看板がさがっていた。
「さあ、飯だ飯だ」
「このお店のご飯、おいしいんだよ」
「へえ、それは楽しみだな」
カランカランカラン……
店の扉を開けると、小さな鐘の音が店内に響く。
「いらっしゃいませ」
秋次たちを出迎えたのは、青いロングヘアで落ち着いた感じのする、眼鏡がよく似合う女の子だった。
「あ、リアンちゃんだ」
「あら、美悠ちゃんいらっしゃい」
そう言ってリアンはニコッと微笑んだ。
「よ!」
「椎奈さんも、それと……」
「ああ、こいつは秋次っていう昨日こっちに引越してきたあたいの従兄弟なんだ。ちょくちょくここに来ると思うんで
よろしくな」
「初めまして。遠藤秋次です」
「『HONEY BEE』へようこそ。私はリアンと申します。このお店でアルバイトとして働いてます」
「外国の方なんですか?」
「ええ、まあ……」
「日本語、お上手なんですね」
「はい。あ、それより席に案内するのが先でしたね。それでは、こちらへどうぞ」
そう言って秋次たちを先導するリアン。
「ところでリアン」
席に着いたところで椎奈がリアンに話し掛ける。
「はい?何でしょう」
「あたいに『さん』づけするのやめてくれないかな。大体、リアンのほうが年上なんだしさ」
「え?そうなの?」
秋次はてっきり美悠と同じくらいかと思っていた。
「はい。でも、椎奈さんは椎名さんですし……」
「その敬語もどうにかなんないの?」
「はあ、そう言われても……」
「お姉ちゃん、リアンちゃんいじめちゃだめだよ」
美悠が頬を膨らませて椎奈に抗議する。
「別にいじめてるわけじゃねーんだけど」
「でも、リアンちゃん困ってるよ」
「だあ、わーったよ」
「ふふ、有難う美悠ちゃん」
「えへへ」
「あの……」
控えめに秋次が声をあげる。
「注文いいですか?」
「え?あ、はい、もちろん」
「なんだ秋次、もう決まったのか?」
「うん。僕は始めてのお店では絶対エビフライ定食を頼むことにしてるんだ。ありますよね?」
「……秋次、そんな定食ない店の方が多いんじゃないか?」
「あったよ。……2割くらい」
「安心してください。うちにはありますから。で椎奈さんと美悠ちゃんはいつものでいいかしら?」
「おう」
「うん、いいよ」
「それじゃあ、ちょっと待っててくださいね」
そういってリアンはカウンターの奥へと消えていった。
「リアンさんが料理するの?」
「まあ、やる時もあるけど、大体はマスターか結花が作ってる」
「結花?」
「ああ、この店のマスターの娘さんさ。でも、今はいない……お、ちょうど帰ってきたみたいだ」
・・・・・
第十話 「飯、堪能する美味」
「けんたろ〜、お腹すいたよ〜」
多少甘えたような声をあげながら『HONEY BEE』に入って来たのは、ピンクの髪の女の子だった。
「わかってるってば、スフィー」
その後ろから、大学生くらいの男が姿を現す。
「ほら、もう着いたじゃない」
さらにその後から、男と同い年くらいのショートカットの女性が入ってきた。
「結花!どこに行ってたんだ?」
「あら、椎奈ちゃんに美悠ちゃん、いらっしゃい」
椎奈が一番最後に入ってきた女性に声をかけると、その女性、江藤結花はにっこりと笑顔を向けた。
「スフィーと健太郎も今から昼飯か?」
「うん、そうだよ。あれ、そっちの人は?」
ピンクの髪の女の子、スフィーが秋次のほうを不思議そうに見ている。
「ああ、こいつは昨日この町に引っ越してきたあたいの従兄弟で、秋次っていうんだ」
「ども、遠藤秋次です」
そう言って秋次はぺこりと頭を下げた。
明らかに、スフィーのほうが秋次よりも年が低そうだが、秋次はつい敬語を使ってしまう。
どうやら、丁寧な喋りは秋次の癖らしい。
「わたしはスフィー、よろしくね。ほら、けんたろも挨拶しなよ」
「ああ、わかってるって。俺は宮田健太郎。今はいろいろあって、この近くにある『五月雨堂』っていう骨董屋を経営
してるんだ。ま、興味があったら暇な時にでものぞいてくれないか」
「骨董ですか?」
「ああ。確かに高価な物も置いてるけど、君のお小遣いで買える物もあるよ。なんたって、美悠ちゃんはうちの常連さ
んだしね」
「え、そうなの?」
美悠は黙ってうなずいた。
「椎奈も、たまには寄ってくれてもいいんじゃない?」
「あたいは、ああいう静かな場所は苦手なんだ」
「う〜ん、椎奈ちゃんにも骨董の良さをわかってほしいな」
「お待たせ〜」
秋次たちが骨董について熱く語っていると、いつのまにか着替えた結花が料理を運んできた。
「え〜と、秋次くん、だっけ?」
「そうです」
「はい。エビフライ定食。で、椎奈がスペシャルランチの美悠ちゃんがお子様ランチでよかったのよね」
「ああ」
美悠は、恥ずかしそうに首を何度も縦に振っている。
「美悠って、お子様ランチ好きよね。ま、確かにここの料理は何でもおいしいんだけど」
「そういうスフィーだって、いっつもホットケーキじゃねーか」
「えへへ。まあね」
「ねえ、もう食べてもいい?」
控え目に、美悠が聞いてくる。
「ああ、そうだな。冷めないうちに食べるとするか。それじゃあ……」
「いっただきま〜す」
椎奈たち三人は、手を合わせて食前の挨拶をした。
「……息、ぴったりね」
その様子を見ていた結花がそっと呟く。
「こ、これは……」
ふと、秋次の箸が止まる。
「ん?どうした?」
「う………」
「う?」
「うまい!うますぎる!!こんなにうまいエビフライは初めてだ!!!」
「おいおい、おおげさだな」
「ふふ、有難うございます」
いつの間にか秋次たちのテーブルの近くにリアンがやってきていた。
「あ、リアン。今、休憩?」
「うん、姉さん。姉さんのホットケーキは今、結花さんが焼いてくれてるから」
「やった♪」
「あの、俺、オーダーまだすんでないんだけど……」
「ああ!すみません、健太郎さん。すぐ結花さんに通しますから。何にしますか?」
「それじゃ……」
「ナポリタン」
そう言って健太郎の前に、ナポリタンが、ぽん、と置かれた。
「結花……」
「心配しなくても、ちゃんとあんたの分も用意してるわよ。はい、こっちがスフィーちゃんのホットケーキ」
「わ〜、待ってました」
「それじゃ、ごゆっくり」
「待ちな、結花」
「何?椎奈」
「あたいたちはもう帰るから、勘定を頼むよ」
「ええ、いいわよ」
こうして、椎奈たちは勘定をすませて『HONEY BEE』を後にしたのだった。
第十一話 「時、解けゆく心」へ