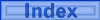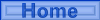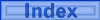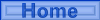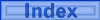坂道までの助走距離
「お姉ちゃん、ちょっといい?」
夜、私が明日の予習をしていると、妹の椋が部屋の外から声をかけてきた。
「ん?鍵は開いてるわよ」
私はそう言って、ノートに走らせていたシャープペンを置いて一息つく。
椅子をひき、机から離れると、ちょうど部屋に入ってきた椋がベットの隅に腰を下ろすところだった。
「どうしたの?こんな時間に珍しいわね」
時刻は午後11時をちょっと回ったくらいのところ。
女子高生が起きていても別に不思議じゃない時間だけど、椋はいつもだいたいこの時間に就寝していたはずだ。
私はどっちかというと夜更かしするほうだけど。
「あのね、お姉ちゃん明日お弁当忘れるから」
「………………は?」
いきなり何を言い出すのだろう、我が妹は。
「あ、占いでそう出たの」
「ああ」
なるほど。
椋の趣味は占いなのだ。
とはいっても、タロットなどを使った本格的なものではなく、椋はトランプを使って占っている。
その占い方も独創的だけど、占いの結果はなぜか妙に具体的なものが多い。
しかも、確実に外れる。
慣れない頃はそれで何度か痛い目を見たけど、パターンさえ掴めばなかなか便利なものだ。
「で、お弁当を忘れるとどうなるの?」
「うん。お姉ちゃんは購買でカツサンドを買おうとするんだけど、あんパンしか買えないの。それで教室でそのあんパンを食べ
てると優しい男の子が『お嬢さん、よかったらこのパンも食べないか?』ってそっとカツサンドを差し出してくれるの。そして二
人で仲良くお昼を食べるんだ」
「……………なんだか、いつも以上に具体性抜群ね…………」
「ちょっと、頑張ってみた」
へへ、と笑う椋。
この、ちょっと照れたような笑顔が私は好き。
双子なんだし、私も同じ表情ができるはずなんだけど、それをやると妙に背筋が寒くなるので封印してしまった。
「わかった、気をつけとく。ありがとね」
「じゃあお姉ちゃん、おやすみ」
「うん、おやすみ」
笑顔で椋を見送る。
「さて、と」
なんだかもう一度机に向かう気もしないので、そのままベッドに入る。
さっきまで椋が座っていたところに、ほんのり温もりが残っていて、ちょっと幸せな気分。
その椋の占いによると、私は明日お弁当を忘れるらしい。
ということは、明日お弁当さえ忘れなければ、その後の具体的な事象は何も起こらないということなんだけど。
それだと、ちょっと面白くない気がする。
だから私は、明日はお弁当は持っていかないことに決めた。
その後どうなるか、それは神様にもわからないんじゃないだろうかと、そう思った。
次の日、私は少し寝坊をした。
毎日の弁当はいつも私が作っているので、ちょっと手抜きになってしまったけど椋の分は作ってあげた。
椋に怪しまれないように私も空の弁当箱を持って行く。
そして、その日の昼休み。
「あれ?今日は弁当じゃねーのか?」
「何、朋也。あんた今頃来たの?」
私が教室を出ようとしたところ、鞄を持って教室に入ってくる男子に出くわした。
名前は岡崎朋也。遅刻の常習犯で、素行不良の問題児。
「ああ、悪いかよ」
「悪いに決まってるでしょうが」
ただ、口や生活態度は悪いけれど、基本的にお人よしなんだなと、話してるうちにそう思うようになった。
「そんなことより学食行くんだろ?なんか買ってきてくれ」
「あんた、それがたった今学校に着いた人間が言うセリフかしら?」
「しょーがねーだろ、春原の奴もまだ来てないみたいだしな」
春原というのは、いつも朋也とつるんでいる悪友の名前だ。
私は下の名前の陽平で呼んでいる。
陽平も、朋也と同様に不良のレッテルを貼られている。
まあ、あいつの場合は不良というより不良品に近いけど。
「まったく。ほら、行くわよ」
私は、朋也の手を引いて歩き出した。
「おい、何すんだ杏」
「早く行かないと学食座れなくなるでしょ」
予定変更。
椋には悪いけど、私は朋也と学食で食べることにした。
まあ、ある意味予定通りというわけかしらね。
「待て、つーかとりあえずこの手を離せ」
「い・や♪」
思いっきり悪戯っぽい笑みで返してあげた。
「しっかし、相変わらずすごい混雑だな」
教室を出るのが少し遅かったから、学食は既に人手溢れていた。
「私が席探しておくから、朋也は私のきつねうどんを買っておいて」
「ああ。ほい」
「何、その手」
「お金」
「あんた、こんな可愛い女の子と食事出来るって言うのにケチケチしないの」
「お前、自分で言ってて恥ずかしくないか?」
「事実だし」
「へいへいわかりましたよ」
そう言ってやや疲れた様子で朋也は食券を買いに向かった。
こうした冗談っぽいやりとりを出来るのは、朋也だけ。
この学校が進学校なせいか、基本的に男子も女子も頭が固い。
だから、不良と言われている朋也と妙に波長が合ったのは、嬉しい偶然だった。
「この辺でいいかしらね」
隅のほうにちょうど空いてる席があったのでそこに腰を下ろす。
と同時に、
「あ、その席僕が先に見つけてたんだけどな〜」
妙に軽い口調が聞こえてくる。
というか、聞き覚えがありまくる声。
「僕たち今からそこでご飯食べたいんだけど〜。どいてくれる?」
「おい、春原……」
「あ〜ら陽平さん、お久しぶり。そんなに私の漢和辞典がお気に召して?」
「ひぃっ!藤林杏!どうしてお前がここに!」
「たまには私だって学食で食べる時もあるわよ」
「ああ、僕に安住の地はないのか……」
「ないわね」
「ないな」
「断言っスか!っていうか岡崎まで!」
「そんなことより早く飯食おうぜ」
「そうね。うどんがのびちゃうわ」
「あの、僕の席は?」
「そこでこれでも食ってろ」
そう言って朋也が陽平に投げ渡したのは、あんパン。
「…………岡崎、確か僕が買ったのカツサンドだったよね?」
「すまん、あれならもう食った。なんなら戻そうか?」
「いらないよ!ちくしょう、グレてやるっ!!」
そう言って陽平はあんパンを握り締めたままダッシュで去っていった。
「いや、俺らもう不良だし。なあ?」
「私は違うわよ」
そう言って、私はきつねうどんのスープを飲み干した。
「さて、そろそろ戻りましょうか。朋也、あんた次の授業出席危ないんでしょ?」
「そうだが、なんでお前が知ってんだ?」
「あれ、そういえばなんでかしらね?」
なぜだろう、胸が一瞬ざわついた。
「は?」
「まあいいじゃないそんなこと」
私はその胸の異変を覆い隠すように、急いで教室へと戻った。
その日の夜、私は椋に今日あったことを話した。
「それにしても、なんでかしらね。別に朋也の出席日数なんか数えてるわけでもないのに」
「それは、お姉ちゃんがいつもその人のことを見てるからなんじゃないかな」
「え?」
椋の言葉に、思わずドキリとした。
「だから自然と、その人のことがわかるんだよ」
「そうかしらねぇ」
改めて思い返す。
私はそんなに意識して朋也を見たことはない。
と思う。
「でもそれって………」
そこまで言って、椋は言葉を止めた。
「何?」
「ううん、なんでもない」
「そう」
私も、椋が言おうとしている言葉はなんとなく見当がついている。
でも、まだそれが言葉として形を成すものかどうか、自分でもわかっていない。
その後は、椋と他愛ないお喋りをして就寝までの時間を過ごした。
それを恋だと確信するのは、もう少し先の話。
─ Fin ─