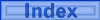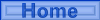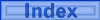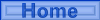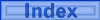星降り注ぐ公園で
「今日はとっても星が綺麗ですね、祐一さん」
「ああ、そうだな」
公園のベンチに肩を並べる祐一と栞。
「もう、そんな時はドラマみたいに『お前の方が綺麗だよ』って言ってくれなきゃヤです」
「そんな恥ずかしいこと出来ねーっつうの」
「え〜、でも、夜の公園で待ち合わせってなんだかドラマっぽかったでしょ?」
「そりゃあ、な」
「だったらもうちょっとノってくれてもいいじゃないですか」
「ただなあ。アイス食いながら待ってるドラマのヒロインはいないと思うぞ」
「そんなこと言う人嫌いです」
ぷい、と顔を横にそむける栞。
「悪かったよ、栞」
「じゃあ、祐一さんも一緒にアイス食べましょう」
「……それは勘弁してくれ」
ちなみに、雪は降ってなくとも今は12月。
明らかにアイスの季節ではない。
「せっかく用意したのに……食べてくれないなんて、酷いわ。よよよ〜」
「いや、そんなしな作っても食わないもんは食わないからな。ってか、どこでそんな仕草覚えたんだよ」
「うっ、持病の癪が……」
「時代劇にハマってるのか?」
「そういうわけですから、どうぞ召し上がれ♪」
「……さっきの演技との関連性が皆無なんだが……」
とつぶやきつつも、ついついアイスを手渡されてしまう祐一であった。
「どんどん食べてくださいね。おかわり自由ですから」
「遠慮しとくよ。にしても栞、お前いつもアイス持ち歩いてるのか?」
「必須アイテムですから」
「どうでもいいことだが、その4次元ポケットにはもうちょっと役に立つもの入れといたほうがいいと思うぞ」
「え〜、入ってますよ」
「で、何が入ってるんだ?」
「アイスとかアイスとか……あと、アイツとか」
「アイツ?!アイツって誰だよ?」
「あ、間違えました。アイスでした」
てへっ、と舌を出す栞。
「アイツのことが非常に気になるが、聞くのも恐いのでそういうことにしておくか」
「はい、そうした方が身の為ですよ」
「……俺、今日はもう帰るわ」
「そうですか、残念です。では、お別れのキスを……」
そういって栞は祐一の頬に軽く口づけた。
「ちゅっ♪」
その後、栞は満面の笑みで、
「はい、これプレゼントします」
と、十数個のアイスが入った袋を祐一に渡した。
「それを私だと思って食べてくださいね〜。今日中に」
ちなみに、今日はあと2時間ほどで終わろうとしている。
「出来なかったらおしおきです♪12時頃電話しますから〜それでは〜」
言いたいことだけ言って、栞は去っていってしまった。
「……食うのか?これを?」
手に持ったアイスを見つめ、ただただ立ち尽くす祐一であった。
お・し・ま・い♪