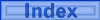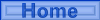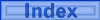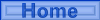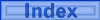天野亭へようこそ!
「いらっしゃいませ」
扉を開けた瞬間、祐一の手が止まる。
そして、もう一度扉を閉める。
隣りの名雪に確認。
「なあ、ここって“百花屋”だよな?」
「うん、昨日もここでイチゴサンデー食べたよ」
「よし……」
意を決して再び扉を開ける祐一。
「いらっしゃいませ」
そして再び聞こえる先程と同じ声。
祐一の視線の先に映るのは、和服姿で頭を垂れる天野美汐の姿であった。
もちろん、名雪にも同じ光景が見えている。
またまた店の中へは入らずに、扉を閉める祐一。
「……今の、天野だよな」
「うん、そうだね」
とりあえず名雪に確認。
「ふと思ったが、百花屋って横開きのドアだったか?」
「違うよ。押すと開いてチリンチリンって音がするんだよ」
「座敷なんてあったか?」
「カウンターとテーブルで、座敷はなかったよ」
「……今、中見た限りじゃ、全席座敷だったぞ……」
「不思議だね〜」
「っていうか、ここは本当に“百花屋”か?!」
上を見上げる。
そして、店の名を記すその看板には大きくこう書かれていた。
「“天野亭”?!」
「でも、場所は百花屋の場所だよ」
「よし、天野に直接聞いてみよう」
三度扉を開く祐一。
「冷やかしはお断りです」
が、今度は美汐に先制攻撃を食らう祐一。
「追い出されちゃったね」
「ああ、仕方ない。帰るぞ名雪………って、待てい天野!」
四度目に開かれた扉から、やっと店の中へと突入する祐一&名雪。
「4回。意外と早かったわね」
「おかしいな。後2回は躊躇すると思ったんだけどな〜」
「香里!北川!お前たちどうしてここに?!」
店内に入ってすぐの席に、見知った顔があったことに驚く祐一。
「多分、あなたたちと同じ理由よ」
「あ、じゃあデート?」
笑顔で問いかける名雪。
「それだけは断じて違うわ」
神速で返す香里。
へこたれる北川。
「そうだぞ、名雪。俺たちも別にデートしてるわけじゃないだろ。ただお前がどうしても百花屋でイチゴサンデー食いたい
っていうから仕方なく……」
「申し訳ありませんが、当店にそのようなメニューはありません」
すすっと祐一たちの間に入りこむ美汐。
「うぉ?!天野、いつの間に?」
「それよりも早く席へついてください」
いつもと変わらぬポーカーフェイスで祐一たちに着席を促す美汐。
「それもそうだな。じゃあ、香里たちと相席でいいか?」
「私は構わないよ♪」
「ええ、私も構わないわよ」
「以下同文」
というわけで、同じ席についた祐一、名雪、香里、北川の四人。
ちなみに、香里と北川が向かい合わせに座っているので、祐一は北川の隣りに、名雪は香里の隣りにそれぞれ座る。
結果として祐一と名雪も向かい合わせで座ることになった。
「ところで、お前たち注文はもう済んだのか?」
「まだよ」
「ちょうど注文しようとした時に、相沢たちが入ってこようとしたんだよ」
「私イチゴサンデー大盛り♪」
「まあ、名雪はほっとくとして、香里たちの注文は決まってるんだな」
「決めるまでもなかったけどね」
「ああ、そうだな」
「?どういうことだ?」
くい、と机のはじにある“お品書き”を示す香里。
「え〜と、どれどれ………『おしるこ』『ぜんざい』……ってこれだけか!」
そう、祐一が開いて見ているその“お品書き”には、左側に『おしるこ 250円』右側に『ぜんざい 300円』という
文字だけが記されていた。
「なんでぜんざいのほうが高いんだろうね?」
「そんな問題じゃないだろ!どうなってんだよこの店は。責任者出てこい!」
「はい。お呼びでしょうか?」
つつつ、と寄って来る美汐。
「やっぱりお前が責任者だったか……」
「“天野亭”ですから」
「で、その責任者のお前に一つ聞きたいことがある」
「はい、なんでしょう?」
「どうしてここのメニューには『おしるこ』と『ぜんざい』しか存在しないんだ?」
「それは……」
珍しく言い淀む美汐。
「美味しいですから。つべこべいわずに頼んじゃってください」
「よし、わかった。じゃあ、おしるこ……って、なんでだ!答えになってねーよ!!」
「出たわね、相沢君必殺のちゃぶ台返し」
「まあ、ここの机は固定型みたいだから実際にひっくり返りはしないんだけどな」
「ねえ、天野さん。イチゴサンデーまだ?」
「わかりました。ぜんざい4っつですね。少々お待ち下さい」
すたすたと去っていく美汐。
「待てい!客のオーダーを無視した注文を受けつけるのか、この店は」
「冗談です」
くるっと振り返る美汐。
「それから水瀬さん、うちにイチゴサンデーは置いてませんので」
「じゃあ、おしるこにイチゴのトッピング!」
「おいおい、そんなこと出来るわけない………」
「かしこまりました」
「って、出来るのか?!」
す、と店の壁に貼ってある壁紙を指し示す美汐。
そこには“各種トッピング受け付けております”と書かれていた。
「マジか……」
「わ〜い♪」
「………絶対マズイと思うけどな」
「で、相沢さん。ご注文は?水瀬さんと同じでよろしいですか?」
「それだけは絶対にゴメンだ」
強い拒否を示す祐一。
「で、香里たちはもう頼んだのか?」
「私、ぜんざい」
「俺、おしるこ」
「むう、無難な選択だな」
「只今、キャンペーン期間中なのでトッピングは無料ですよ?」
「そうなのか?……って、この店はいつオープンしたんだ。ついでに、ここは昨日まで百花屋だったはずだぞ?」
「相沢さん、そんな些細なことは気にしないでください」
「それよりも、私は客が私たち以外いないことのほうが気になるんだけど……」
「そういやそうだな」
「美坂さん、北川さん、世の中には知らなくていいことのほうが多いんですよ?」
「イチゴ♪イチゴ♪」
一人浮かれている名雪。
「もう、これ以上の詮索はなし。いいですか?いいですね?いいですよね?良くないことなんかありはしませんよね?」
ずい、ずい、ずいと祐一たちに迫る美汐。
「お、おう」
迫力に押され承知する祐一。
「……わかったわ」
しぶしぶといった感じで承諾する香里。
「すみませんでした」
何故か謝る北川。
「了承だお〜」
そして秋子さん譲りの了承を返す名雪。
「で、相沢さん。注文はお決まりですか?」
「そうだな、じゃあぜんざいにしよう」
「それとイチゴのトッピングだね〜」
「それはいらん」
「え〜美味しいのに〜」
「それでは注文を繰り返します。ぜんざいがお二つ、おしるこがお一つ、おしるこのイチゴあわせがお一つ。以上で注文は
よろしいでしょうか?」
「ああ、OKだ」
「かしこまりました。では、ごゆっくり」
ぺこりと頭を下げて、すたすたと去っていく美汐。
「そういや、ふと思ったんだが……」
美汐の後ろ姿を見送りつつ、祐一が呟く。
「天野って料理出来るのか?」
「そんなこと、私に聞かれても知らないわよ」
「俺も知らん」
「私も知らないよ〜」
「う〜ん、まあ、あゆほど酷くはないと思うが。それに、ぜんざいとおしるこだからな……まあ、食えないことはないだろう」
「お待たせしました」
そうこうしているうちに、お盆に注文の品を乗せた美汐がやってきた。
「おお、普通だ。……アレ以外は」
「なんか、見てるだけで胸やけしそうね……」
「………」
「わ〜い、イチゴたっぷりだよ〜」
「サービスしておきました」
お椀に山盛りの小豆まみれのイチゴ。
それを名雪の前にそっと置く。
そして普通のおしることぜんざいを配る美汐。
「ご注文は以上でよろしかったでしょうか?」
「ああ」
「あ、これデザートのメニューです」
そう言って脇に抱えていたメニューをテーブルに置く美汐。
「なんだ、デザートは別メニューでちゃんとあったのか」
「……私、おしるこやぜんざいもデザートの類だと思うんだけど」
「まあ、細かいことは気にするな。え〜と、どれどれ………『おはぎ』………だけ?」
「はい」
「オンリー?」
「オンリーです」
「………ごちそうさま」
デザートメニューをそっと美汐に返す祐一。
「そうですか」
ちょっとだけ残念そうな美汐。
「祐一、早く食べようよ〜」
もう待ちきれないといった感じの名雪。
「ああ、わかったわかった。それじゃあさっさと食っちまおうぜ」
「わ〜い♪」
「では、いただきます、と」
それぞれに食前の挨拶をして食べ始める四人。
そしてそれをじっと見つめる美汐。
「……なあ、天野。どうしてそこで俺らが食べる様を見つめてるんだ?」
「気にしないでください」
「気になるっちゅうねん!」
何故か関西弁でつっこむ祐一。
「じゃあ、隠れて見てますね」
そそと机の陰に隠れる美汐。
「……余計気になるって」
「じゃあ、一体どうすれば」
「はぁ、もうどうにでもしてくれ」
すっかり疲れ果て、美汐の説得を諦めた祐一。
「やっぱりイチゴはおいし〜ね〜♪」
幸せそうにイチゴおしるこを頬張る名雪。
「……名雪見てると、なんだか食べる気なくすわね」
「美坂の意見に一票」
「え〜、美味しいよ?」
「そりゃ、あんたは美味しいんでしょうけどね」
はぁ、とため息を吐く香里。
「うん、これ一つでごはん6杯は軽いよ〜」
「それでは、おはぎ6個をお持ちします」
そそと店の奥へ行こうとする美汐。
「待てい天野!今の会話のどこにおはぎが出てきた?」
慌てて制止する祐一。
「水瀬さんがごはんが食べたいと」
「まあ、あれは名雪なりのどれだけイチゴが好きかという比喩だから余り気にしないでくれ。でも実際名雪だったら食い
かねん……」
う〜む、と悩み出す祐一。
「でもやっぱりおはぎじゃダメだ。ちゃんとした白ご飯じゃないとな」
そういう結論に行きついたらしい。
「そうですか。残念です」
「っていうか、おはぎあるんなら白ご飯も出せるんじゃないのか?」
「それは無理な相談です。この店は和風が信条なもので」
「……白いご飯も十分和風な気がするけどな」
なんとなく小声でそんなことを言ってみる祐一。
「相沢さん、その言葉、私の目を見て言えますか?」
薄っすらと微笑む美汐。
「遠慮しとくっス」
「ふう、お腹一杯だお〜」
いつの間にかおしるこ&イチゴを食べ終えた名雪が、ぽんぽんと軽くお腹を叩く。
「太るわね」
「太るだろ」
「むしろ、太らなければならない」
「太ってます」
これが、皆が名雪の食いっぷりを見た感想だった。
「天野、それはちょっと言い過ぎだぞ。いくら事実だとしてもだ」
「冗談です」
「祐一のほうが酷いよ〜」
テーブルをぽかぽかと叩いて祐一に抗議する名雪。
「わかった、悪かったよ。でもお前、最近甘いものばっかり食ってるだろ?」
「ちゃんと運動してるから大丈夫だよ〜」
「そうか?今、体重どのくらいなんだよ?」
「祐一、女の子にそんなこと聞いたらダメなんだよ!」
「47kgです。水瀬さんの体重」
「な……」
「なんで天野が名雪の体重知ってるんだ?!」
「勘です」
「なんだ、勘かよ。断言するからてっきり身体測定の結果でも盗み見たのかと思ったぜ」
「でも、当たってるみたいですよ」
そう言って、名雪を指差す美汐。
当の名雪はというと、その場で絶句し直立不動の態勢で固まっていた。
「う〜む、これは本当に当たってるみたいだな。おい、名雪、戻ってこい!」
名雪の肩を揺さぶる祐一。
「………はっ!!あ、天野さん惜しいな〜。本当はもう少し軽いんだな、これが」
「名雪、いまさらフォローしても遅いわよ」
「そうだぞ、名雪。それに、別に隠すほどの体重じゃないじゃないか」
「う〜、祐一は乙女心がわかってないんだよ〜」
「そりゃわからんさ。俺は乙女じゃないしな」
「俺はちょっとだけわかるぞ?」
「何!北川、お前“ちょっとだけ乙女”だったのか?!」
「……名雪、バカ二人はほっといて帰りましょ。天野さん、精算いいかしら?」
スタスタとレシートを持ってレジの方へと向かう香里。
「ああ、美坂の愛が痛い……」
「……お前、相当重傷だな」
とりあえず北川はほっておいて香里と合流する祐一。
「お会計、全部で3000円になります」
「高っ!おしることぜんざいだけでこの値段は法外だぞ?!」
「この時期、イチゴは高価ですから」
じっと全員の視線が名雪に集まる。
「それに、国産の最高級のイチゴをふんだんに使いましたから」
「よし、じゃあ今日は名雪のおごりだな」
「そうね」
「そうしよう」
「え〜、なんで〜?!」
理不尽な請求に、正当な権利を求め抗議の声をあげる名雪。
「じゃあ、多数決で決めましょう。名雪が全額支払うべきだと思う人は手を挙げて。はい」
「はい」
「はい」
「はい」
何故か美汐の手も挙がる。
「暴力反対!」
「つべこべいわないでさっさと払いなさい!」
「うう〜、わかったよ。払うよ〜」
泣く泣く財布から3000円取り出す名雪。
「ありがとうございます」
「んじゃ、天野ご馳走さん。色々ツッコミたい部分はあるが、ぜんざい美味かったぜ」
「おう、また来るぜ!美坂と二人でな!」
「気が向いたらね」
「イチゴも美味しかったよ〜」
「はい、ありがとうございます。では、今後とも“天野亭”を一つ御贔屓に……」
そう言ってペコリと頭を下げる美汐。
「じゃあ、またな」
「バイバ〜イ」
「失礼するわね」
「お供します」
そんな言葉を残して店を後にする4人。
そして、“天野亭”を出た後しばらく商店街をぶらぶらしていた4人であったが、ふいに香里が祐一に切り出した。
「ねえ、相沢君」
「ん?どうした香里?」
「今、ふと思ったんだけど、あの娘相沢君に『今はキャンペーン中だからトッピングは無料』みたいなこと言ってなかった?」
「ああ、確かに言ってたぞ」
「じゃあ、なんで名雪のイチゴの料金取られたの?あれもトッピングでしょ?」
「……………天野、たばかりおったな!!!」
何故か時代劇口調の祐一。
「ものども、であえー!であえー!敵は“天野亭”にあり!!」
駆けて行く祐一。
「あ、祐一待ってよ〜」
「まったく、お金払ったのは名雪だっていうのに……」
「愛だね〜」
などと口々に呟きつつ祐一の後を追う3人。
そして。
「……百花屋だ」
「百花屋ね」
「まさしく」
「イチゴサンデー♪」
「お前はまだ食うつもりか……」
中に入ろうとする名雪を止める祐一。
「それにしても……」
周囲を見回す祐一。
いつも見慣れた風景がそこにはある。
しかし、天野亭の姿はどこにも見つけることができない。
「つぶれちゃったのかな?」
「まあ、お客が私たちだけじゃその可能性もあるわね」
「……お前たち、なんか根本から間違ってるぞ」
「まあ、いいじゃないか。世の中は不思議で一杯なんだ」
「別に不思議が一杯なのは別に構わんが、一つだけ言わせてくれ」
「ん?まだ何かあるのか?」
「ああ、あるとも」
そう言って祐一は大きく息を吸いこみ、声も高らかにこう叫んだ。
「“おしるこ”と“ぜんざいの”違いってなんだ!!」
「わかる?名雪」
「知らないよ〜。香里は?」
「知るわけないでしょ」
「俺も知らん」
「“おしるこ”が粒なし、“ぜんざい”が粒ありだと思いますよ」
「ああ、なるほど。さすが天野………って、天野?!」
驚いて声の方を見る祐一。
そこにはいつの間にか制服姿の美汐が立っていた。
「お前、いつからそこに?」
「はい、さきほど相沢さんの叫び声が聞こえたので近寄ってみたんです」
「ああ、そういうことか……と、その前にお前店はどうしたんだよ?!」
「お店、ですか?」
「そうだよ〜。ここにあったお店だよ〜」
「ここは百花屋ですよ?」
「まあ、今はそうなんだけどね。私たちが寄った時は別のお店だったのよ」
「別のお店?」
「そうなんだ。その店の名前が“天野亭”っていうんだ」
「はぁ…?」
なんだか不思議顔の美汐。
「そうだ。そして天野、お前はその店の責任者だったんだぞ」
「相沢さんたち、夢でも見ていたのではないですか?」
「でも、イチゴおいしかったよ?」
「あれは夢なんかじゃないわ。そうよね、北川君?」
「もちろん!」
「金だってちゃんと払ったしな」
「名雪がね」
「はぁ……」
なんだか困った様子の美汐。
「あ」
そして何やら思い当たったようだ。
「そういえば、さっき真琴を見かけました」
「ん?それがどうかしたのか?」
「たくさんの肉まんを抱えて足取りも軽やかに歩いてたんです」
「それと“天野亭”と何か関係あるのか?」
「もしや、相沢さんたち、狐に化かされたのでは?」
一同、絶句。
「……マジで?」
「ええ、多分。百花屋にかすかに真琴の気配が残ってますから」
「あいつ、いつの間にそんな大技が使えるようになったんだ………名雪、帰るぞ!」
ダッシュで駆け出す祐一。
「あ、待ってよ祐一〜〜」
後を追う名雪。
残される香里、美汐、北川。
「で、この後どうする?」
「私も帰るわ」
「では、私も」
別れの挨拶を告げ、それぞれの家へと帰る香里と美汐。
一人さびしくたたずむ北川。
「………俺も帰ろう」
「真琴!!!」
家につくなり、大声で真琴の名を呼ぶ祐一。
そして一直線に真琴の部屋へ。
扉を開けるなり一言。
「金返せ!」
しかし、部屋に真琴はいなかった。
そこに居たのは部屋を片付けていた秋子さんだった。
一瞬、祐一の顔から血の気が引いた。
「あら祐一さん、真琴ならリビングでテレビを見てますよ」
「はい」
それだけ告げると、祐一は大慌てでリビングへと向かった。
「こら!真琴!!」
「祐一うるさい!」
「うるさくて構わんから金返せ!」
「へ?」
キョトンとする真琴。
「さっき俺たちから巻き上げただろうが、“天野亭”で!」
「そ、そんなお店しらないもん」
あきらかに挙動不審だ。
「じゃあ、この目の前の肉まんはどうやって手に入れたんだ?」
「拾ったの」
「嘘つけ!」
ぺしっと真琴の頭を叩く祐一。
「あぅ〜。でも、お金払ったのって名雪じゃない!なんで祐一に返さなくちゃいけないのよ!」
「ほう。なんで金を払ったのが名雪だって知ってるんだ?」
「え?えと、それは〜……………ゴメンなさい」
観念して謝る真琴。
「やっぱり真琴ちゃんの仕業だったんだね」
いままで静観していた名雪がひょっこり現れた。
「ああ。さあ真琴。名雪にお金を返すんだ」
「……いの」
「は?」
「もうお金ないの!」
何故か逆ギレする真琴。
「全部肉まんに使っちゃったの!!」
「な……」
「待って、祐一」
真琴を叱ろうとした祐一を、名雪が止める。
「しょうがないよね?肉まん食べたかったんだよね?」
微笑に迫力がある。
「あぅ〜」
「今日の晩御飯は『アレ』使ってもらうからね」
笑顔が怖い。
「あぅ〜〜〜〜〜」
やはり名雪は秋子さんの娘だと実感する祐一。
「……まあ、これにて一件落着ってわけだ」
「うん、そうだね」
「それにしても、お前よく天野に化けたな。完璧だったぞ」
「え?わたし別に美汐には化けてないよ?私が化けたのはあの店そのものだから」
「な……」
「へぇ〜、すごいんだね真琴ちゃん」
「へへへ〜♪」
「じゃあ、おれたちが話してた天野はもしかして………本物?」
「そうだよ。私美汐からお金もらったんだもん」
「ば……」
驚きのあまり言葉が出ない祐一。
「化かされた!」
美汐が一番の狐だということを思い知った祐一であった。
「またのご来店、お待ちしています」
END